介護現場で働く皆さんの毎日の頑張りに心から敬意を表する、ケアマネージャーの佐藤と申します。
「ご利用者の笑顔のために」「ご家族に安心を届けたい」という思いで、一生懸命に働いている皆さんの姿を見るたび、私は常に深く感謝しています。その優しさと責任感が、介護という仕事を支えているのだと強く感じています。
でも、時々こんな気持ちになりませんか?

「自分のことは、いつも後回しだな…」
「最近、心から笑えていないかも…」
という思いが頭をよぎることもあるかもしれませんね。ご利用者への思いが強いからこそ、自分の限界を超えて頑張ってしまう方も多いです。それは、介護職に携わる多くの方が共感できる悩みなのかもしれません。
この記事では、そんな「がんばりすぎ」な皆さんに向けて、心と体を守るセルフケアや自分らしい働き方を見つけるヒントをお届けします。このページを読み終える頃には、心が少しでも軽くなっていることを願っています。
「がんばりすぎ」は危険信号!あなたの心と体からのサインに気づこう
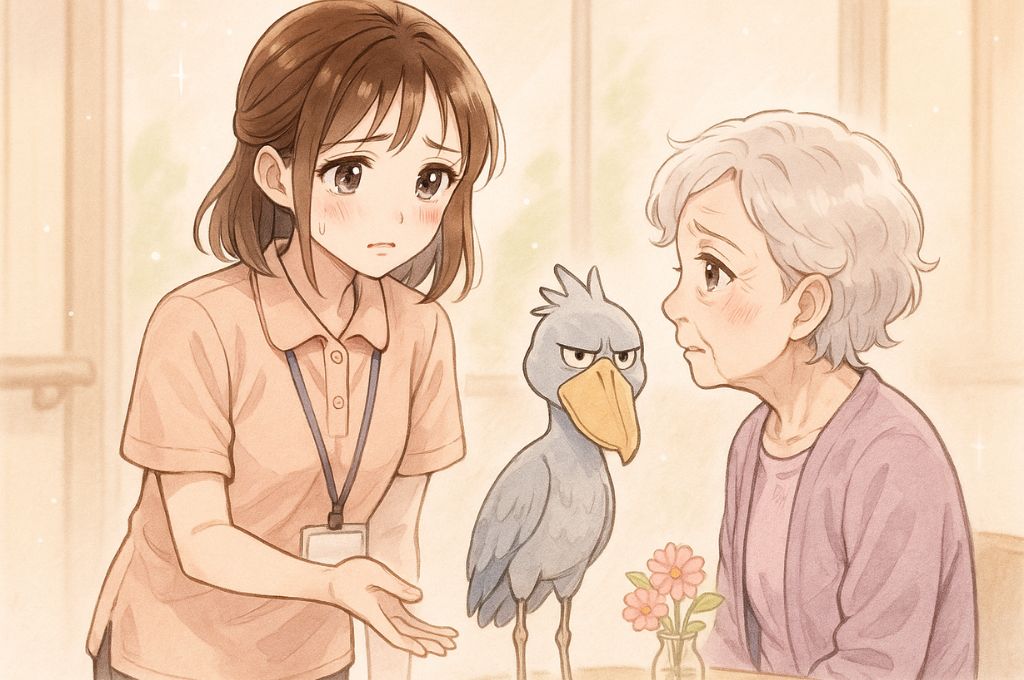
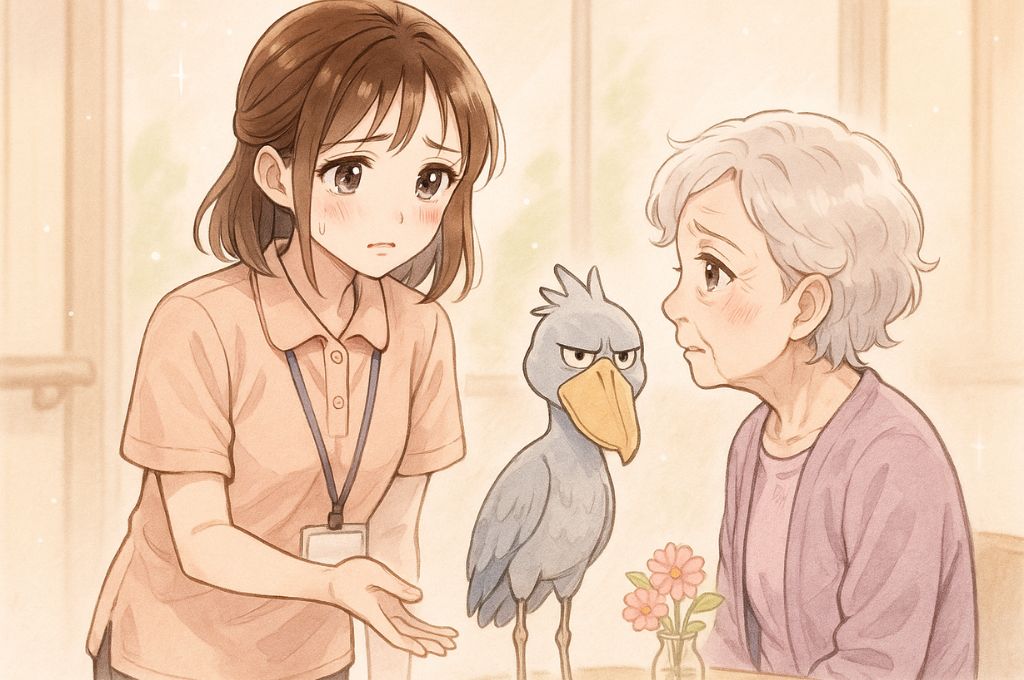
介護の仕事は本当に尊いものです。誰かの心と体に寄り添い、その人の生活に深く関わることで、多くの喜びややりがいを感じられるでしょう。でも、その一方で心身の負担が大きいことも否めませんね。特に真面目で責任感のある方ほど、「自分ががんばらなきゃ」と思いがちになるかもしれません。その気持ちはとても自然なことです。しかし、知らず知らずのうちに自分の限界を超えてしまうこともあります。
まずは、自分自身の状態を冷静に見つめ直してみませんか。「もしかして頑張りすぎているかも」と気づくことが大切です。以下のヒントを試してみてくださいね。
- 日常の中で小さな休息時間を見つける
- 他の人と積極的に話をし、気持ちを共有する
- 自分への褒め言葉をたくさんかけてあげる
- 助けてもらうことにためらわず頼る
やらなければならないことがたくさんあるかもしれませんが、すべて完璧にやる必要はありません。一歩ずつ、少しずつ、自分のペースで進んでいきましょう。あなたは一人ではありません。
介護職にありがちな「がんばりすぎ」パターン
介護の現場でたくさんの方々と接していると、特に「がんばりすぎ」に陥りやすいと感じる状況がいくつか見えてきます。もしかしたら、あなたにも心当たりがあるかもしれません。
介護の現場では、どうしても人手が足りなくなりがちで、「このシフト変わってもらえない?」「残業お願いできる?」といった相談が日常茶飯事ですよね。「みんな大変だから」と思って断れず、気づけば自分の大切な時間が削られてしまうことも少なくありません。あなたの優しさが結果として自分を苦しめてしまうこともあるのです。
「あのご利用者さん、夜によく眠れたかな」「ご家族は不安に感じていないかしら」と、勤務時間外でも仕事のことが頭から離れないことがあります。このように責任感が強い方ほど、仕事とプライベートの境界が曖昧になりがちで、心が常に緊張状態にあるために、十分な休息がとれなくなってしまいます。
「もっと良いケアができたのでは」「自分のミスでご利用者に不便な思いをさせてしまったかも」と、常に完璧さを追い求めてしまうことがあります。高い理想を持つのは素晴らしいことですが、自分を責めすぎると心のエネルギーを消耗してしまいます。介護はチームで行うもの、一人で全てを完璧にこなそうとしなくても良いのです。
これらのパターンは、一つひとつは小さなことかもしれません。でも、続けていくと心や体に大きな負担になっていきます。「これは自分のことかも」と気づいたときは、それが立ち止まって、自分自身を労わるべき大切なサインかもしれません。
- 少しでも無理を感じたら、思い切って「NO」と言ってみる
- 勤務時間外は自分の時間を大切にしてみる
- 全部を完璧にしようとせず、少しずつ自分を労わる
少しの気づきと実践が、新しい心の余裕を生むかもしれません。どうか、ご自分を大切にしてくださいね。
こんな症状に心当たりはありませんか?がんばりすぎのサイン
日々の生活の中で、私たちの心や体が少しずつ疲れてきていると、さまざまなサインを発し始めます。もしかしたら、その変化は小さくて見過ごしがちなものかもしれません。でも、その小さな声をキャッチすることが、深刻な状況を防ぐための大切な一歩なんです。「最近、なんだか変だな」と感じたら、それはただの気のせいではないかもしれません。
- 朝、すっきり起きられないことが続く。
- 疲れが取れず、いつも体が重い。
- 食べ過ぎたり、食欲がない日がある。
- 頭痛や肩こり、腰痛が慢性化している。
- 風邪を引きやすくなったと感じる。
- 趣味が楽しめなくなってきた。
- 些細なことでイライラしたり、涙が出ることがある。
- 仕事でのミスが増え、集中力が続かない。
- 人との会話を避けたくなる。
- 「仕事に行きたくない」と感じる日が増えた。
これらのサインは、「もう少し自分をいたわってほしい」という自分自身からの大切なメッセージです。どうか「自分に厳しすぎないように」と心がけてください。専門的なケアを提供し続けるためにも、まずは自分自身の心と体の声に耳を傾けてあげましょう。それが、より良いケアを提供するための基盤となります。
- 十分な睡眠を心がける。
- バランスの取れた食事を心がける。
- 少しずつ体を動かす時間を作る。
- 自分を責めすぎず、優しく許す。
大切なのは、全部完璧にやろうとしないことです。一歩ずつ、自分のペースで始めてみましょう。あなたの健康が、周囲の方々へ質の高いサポートを提供する礎になります。
がんばりすぎを放置するとどうなる?心身の不調と燃え尽き症候群
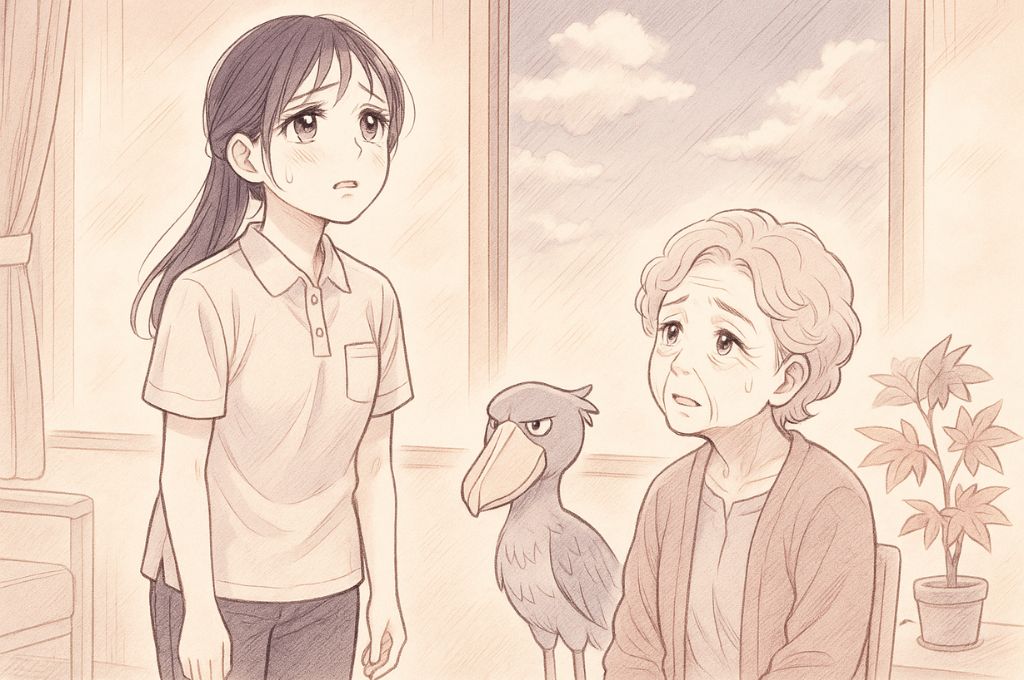
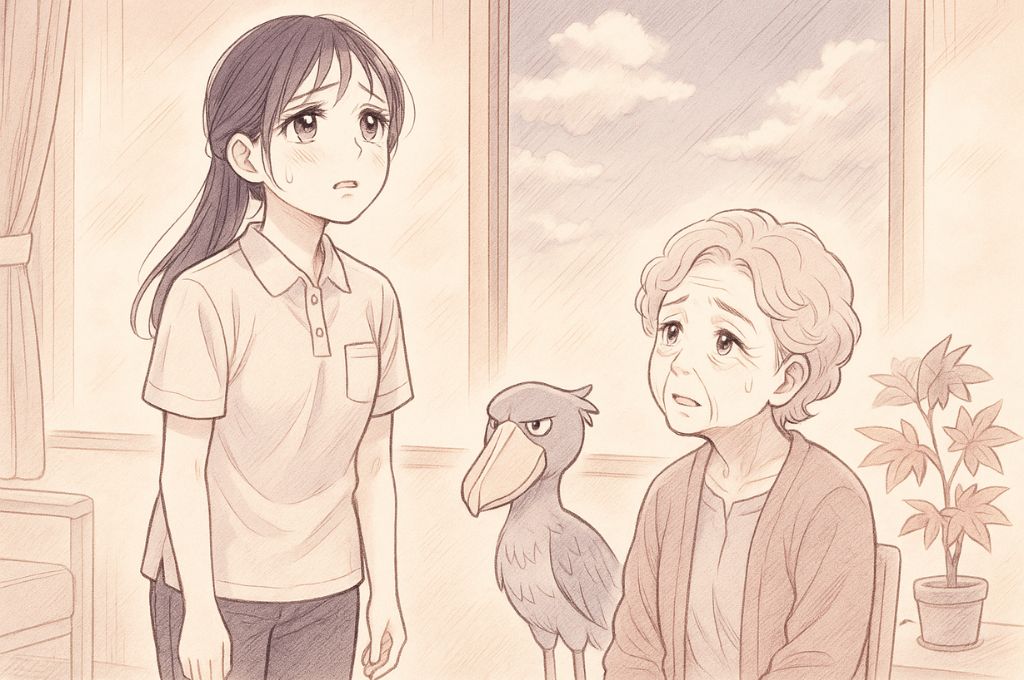
時には「がんばりすぎかな?」と感じることもあるかもしれませんよね。それでも、「まだ大丈夫」「今は休む暇なんてない」と無理をし続けてしまうと、心と体に負担がかかり、もっと大きな問題を抱えてしまうかもしれません。特に介護職の皆さんには、「燃え尽き症候群(バーンアウト)」について知っておいていただきたいです。
燃え尽き症候群とは、一生懸命頑張ってきた方が、心身ともに疲れ果ててしまい、仕事への意欲を失ってしまう状態です。特に介護の現場で働く皆さんにとって、これは決して他人事ではありません。燃え尽き症候群には、次のような3つの症状があります。
気づかないうちに心のエネルギーを使い果たしてしまい、「もう疲れた」「仕事に行くのがしんどい」と感じることが増えます。これまで感じていた仕事のやりがいや喜びが薄れ、気持ちが空っぽになってしまうこともあります。
ご利用者や同僚に対して、距離を置くような態度をとってしまうことがあります。これは、心の負担を少しでも軽くしようとする自然な反応なのかもしれません。親身に接することが難しくなり、淡々とした対応になってしまうことがあるかもしれません。
仕事の成果を感じにくくなり、「自分はこの仕事に向いていないのかもしれない」と思うことが増えます。どんなに頑張っても手応えを感じられず、自己評価が下がってしまうこともあるでしょう。
燃え尽き症候群は単なる疲れではなく、放っておくと心の健康に大きく影響することがあります。最悪の場合、大好きだった介護のお仕事から離れなければならなくなるかもしれません。
そんな事態を防ぐためにも、働き方や心のケアを考えてみましょう。「がんばること」は大切ですが、「がんばりすぎること」は逆効果になってしまうこともあります。あなたが健康であってこそ、温かいケアを提供できるのです。少しでも「危ないかも」と思ったら、勇気を持って一息ついてみてください。
- 1日数分でもリラックスする時間を作る。
- 気持ちを吐き出せる相手と話す。
- 「自分を責めない」考え方を意識する。
無理せず、できることを少しずつ取り入れてみてくださいね。あなたが健康でいることが、何よりも大切なのです。
自分を大切にする視点へシフトチェンジ!自己肯定感を高める考え方
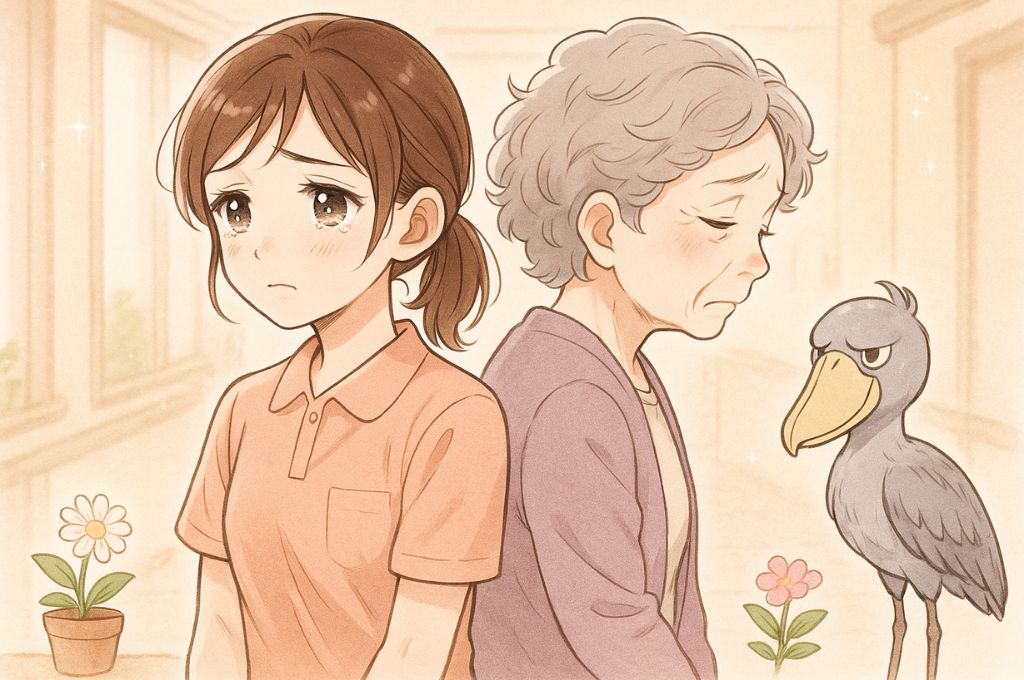
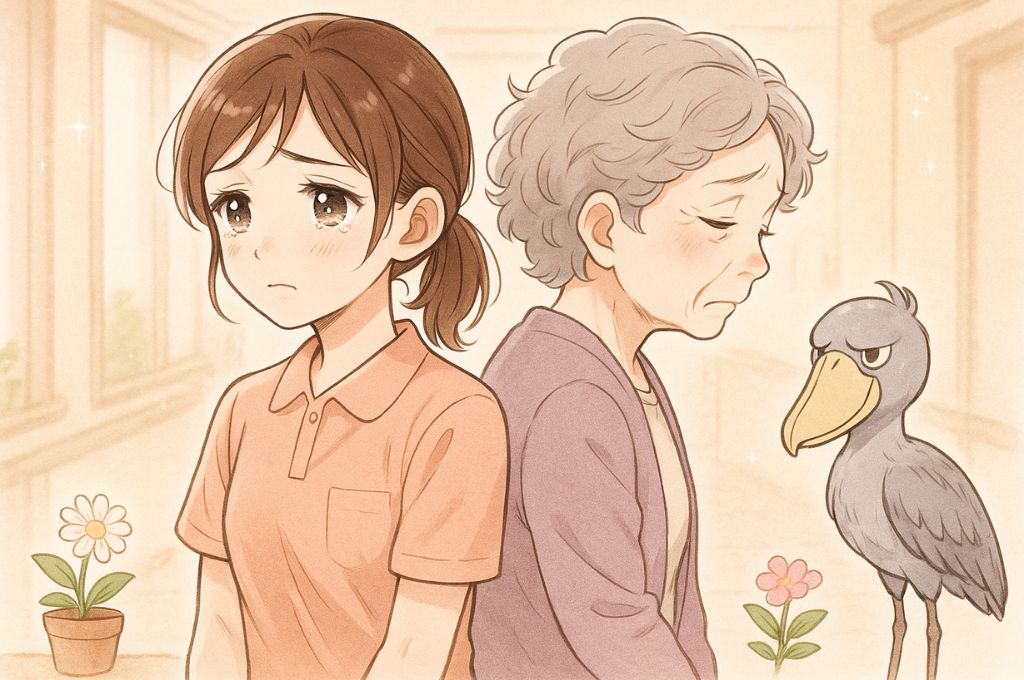
頑張りすぎることがある方へ。このような傾向の背景には、責任感の強さや真面目さに加えて、「こうあるべき」という固定観念や、低めの自己肯定感が隠れていることがあります。心や体を守るためには、まず自分がどのように考える癖を持っているのかに気づき、それを少しずつ変えていくことが大切です。ここでは、自分をもっと大切にするための考え方のヒントを2つご紹介します。
- 自分自身に優しくする: 自分を責めるのではなく、温かい目で自分を見守りましょう。どんな時でも自分の味方でいることが大切です。
- 小さなことを喜ぶ: 日常の小さな成功や喜びを見逃さずに、大切にしてください。どんなに小さな一歩でも、前進です。
すべてを完璧にこなす必要はありません。少しずつ、一つずつ取り組んでみることから始めましょう。それだけでも大きな変化につながります。
「完璧主義」を手放すヒント
介護のお仕事は、人の命や生活に直結する重要なものです。そのため、「ミスがあってはならない」というプレッシャーを感じがちですよね。その結果、気づけば完璧を求めてしまう方も少なくないでしょう。「100点のケアを提供しなければ」とか「常に笑顔でいなければ」といった思い込みで、自分を追い込み、心が疲れてしまうこともあります。
まず、完璧主義から少し解放されるために、「100点でなくてもいいんだ」と自分に許してあげることが大切です。例えば、今日は80点でもOKと思ってみましょう。また、すべてを完璧にこなそうとせず、優先順位を決めることも大切です。
- 記録の書き方を少し簡略化してみる
- 全てのレクリエーションに全力を尽くさず、参加するものと休むものを切り替える
さらに、一人で抱え込まず、周りを頼ることも大切です。介護の現場はチームプレーなので、「この移乗、一人では少し不安があります。手伝ってもらえますか?」や「このご利用者様への対応について悩んでいますが、どう思いますか?」と、同僚や先輩に相談してみましょう。頼ることは「できない」ことを示すのではなく、むしろ質の高いケアを行うためのプロフェッショナルな選択です。周りを頼ることで、自身の負担が減るだけでなく、職場全体のコミュニケーションが円滑になり、チームワークも向上します。
完全な個人を目指すのではなく、チームとしてより良いケアを目指す視点で、肩の力を少し抜いてみてくださいね。
できない自分も認めよう
誰にでも得意なこともあれば苦手なこともありますよね。無理をして頑張りすぎる方は、「できない自分」を受け入れるのが難しいことが多いようです。たとえば、「レクリエーションを盛り上げるのが苦手」とか、「ご高齢者とのコミュニケーションがうまくいかない」といったことで悩んでいるとしたら、「もっと努力しなくちゃ」とか「自分は介護職に向いていないんじゃないか」と思い悩むことがあるかもしれません。
でも、「できない」ことが必ずしも「ダメ」なことではないんです。苦手なことがあるのは自然なことですから、まずは「これは自分にはちょっと難しいかもしれない」と、今の自分をそのまま受け入れてあげましょう。そして無理に克服しようとするのではなく、どうしたらその状況をうまく乗り越えられるかを考えてみましょう。
- レクリエーションが苦手であれば、企画や準備段階でアイデアを出すなど、裏方での活躍を考えてみる。
- 特定のご利用者とのコミュニケーションに悩んでいる場合は、その分野が得意な同僚にアドバイスをもらったり、手助けをお願いする。
こういったように、自分の苦手なところは、チームメンバーの得意な部分で補ってもらうという考え方に切り替えてみるといいかもしれません。
自分の弱さや苦手を認め、それを周囲に伝えることには勇気がいることもありますが、そのおかげで孤立感が解消され、仕事に対する気持ちも少し楽になるかもしれません。そして、自分を責めてしまうエネルギーを、得意なことを伸ばすための力に変えることができるのです。自分自身を受け入れることが、安定した自己肯定感を育む基盤になるんですよ。
心と体をいたわる具体的なセルフケア術
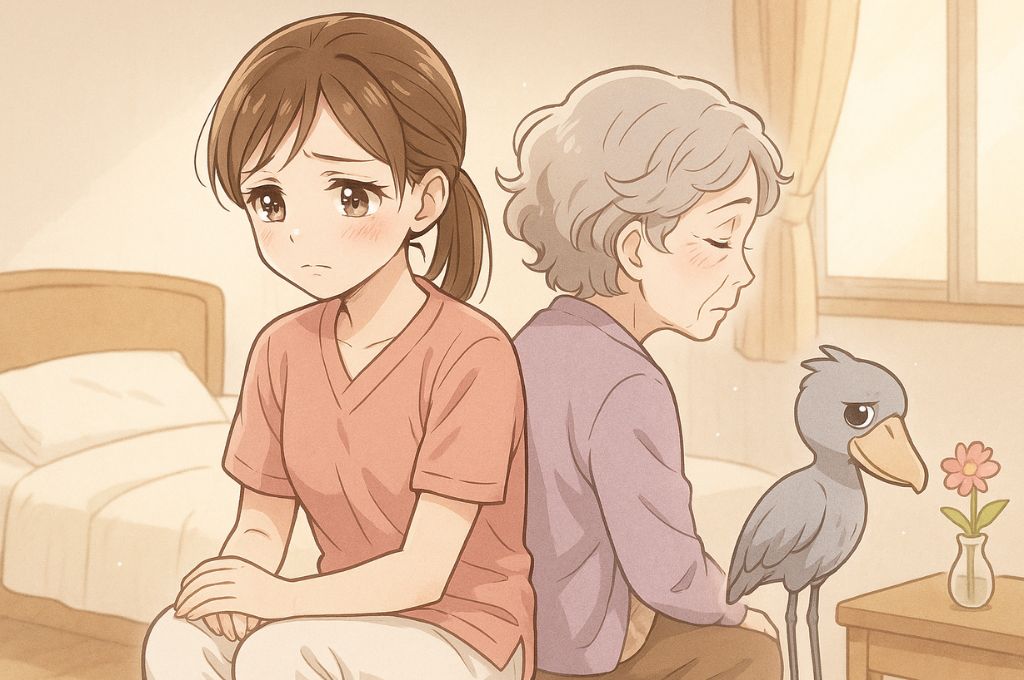
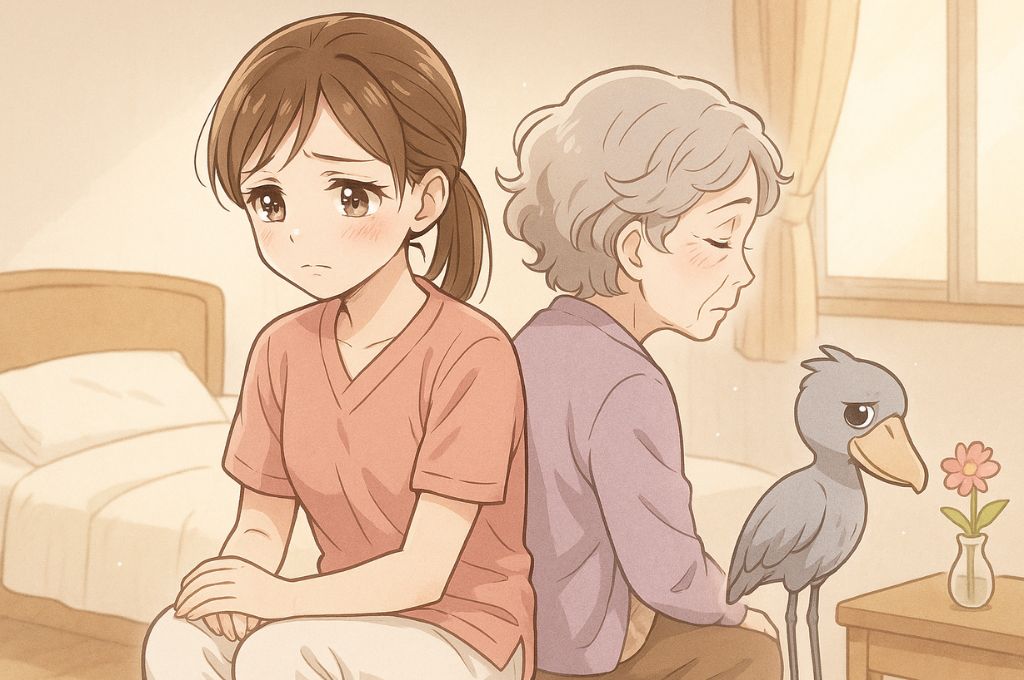
日々の疲れを感じながらも、「少し考え方を変えるだけで心が軽くなるかもしれない」と、ふと考えたことはありませんか?でも、慌ただしい毎日の中で心と体をいたわるために、具体的なセルフケアを習慣にすることもとても大切です。そこで今回は、特にお忙しい方でも簡単に取り入れられる、小さな心身のケア方法をご紹介します。無理をせず、自分に合った方法を見つけて、一歩ずつ進んでみてください。
- ゆっくり深呼吸をして、自分のペースを取り戻す時間を作る。
- 毎日少しの時間でも、好きなことをする時間を確保する。
- 静かな場所で数分間、何も考えずに過ごしてみる。
- 心地よい音楽を聴いてリラックスする。
- 良質な睡眠を心がけ、無理せず休むことを優先する。
これらの小さなステップは、きっと心や体を落ち着かせる手助けになるでしょう。すべてを完璧にやる必要はないので、どうか自分を責めず、今日できることを少しずつ試してみてくださいね。
忙しい日でもできる!心の休憩術
介護のお仕事に携わっているみなさん、日々本当にお疲れさまです。気持ちを張り詰めることが多いこのお仕事、時には意識して心を休めることが大切です。どうか無理せず、少しずつ試してみてくださいね。
ほんの5分だけでも、静かな場所で体を楽にして、ゆっくりと目を閉じてみませんか。呼吸に意識を集中し、「吸って、吐いて」とリズムを感じるだけで、頭の中の不安や思考から解放されることがあります。また、スマートフォンのアプリにあるガイド付きの瞑想も、きっとあなたの助けになるでしょう。
その日に感じたことや嬉しかったこと、モヤモヤしたことをノートに自由に書き出してみましょう。誰にも見せる必要はありません。感情を文字にすることで、心の整理がゆっくりと進むかもしれません。
休日には、思い切って仕事のことを忘れてみましょう。大好きな音楽をたっぷり楽しんだり、感動的な映画を観て涙を流したり、好きな香りでリラックスしたり。あなたが心地よく感じられる方法で、五感を楽しませてあげてください。
どれから始めても構いません。「全部やらなくても大丈夫」です。少しずつ、自分を大切にする時間を増やしていきましょう。
体の疲れを癒やすリフレッシュ方法
心が疲れているとき、それは体の疲れと密接に関係していることが多いものです。少し体をほぐしてリラックスすることで、自然と心も軽やかになるはずです。
シャワーだけで済ませてしまうこともあるかもしれませんが、38〜40度くらいのぬるめのお湯に15分〜20分ゆったりと浸かってみてはいかがでしょうか。血行が良くなり、筋肉の緊張がほぐれます。お気に入りの入浴剤やアロマオイルを使うと、よりリラックスできるでしょう。体が温まることで副交感神経が優位になり、質の良い眠りにつながりますよ。
肩や首、腰など、特に負担のかかりやすい部分を中心に、寝る前や朝起きた時に手軽にできるストレッチを取り入れてみませんか。ゆっくりと筋肉を伸ばすことで血流が良くなり、こりや痛みが和らぎます。YouTubeには、ご高齢者向けのストレッチ動画もたくさんありますので、参考にしてみてください。
休日には予定を詰め込みすぎず、「何もしない日」を作ることも大切です。ソファでゆっくり過ごしたり、好きなだけ昼寝をしたりして、罪悪感を感じずに体を休ませることを自分に許してあげましょう。
何か全部やろうと頑張らなくて大丈夫です。ほんの一歩だけでも試してみてください。それが、心と体への優しい贈り物になるかもしれません。
専門機関に相談することも大切
時には、セルフケアだけでは心や体の不調がなかなか改善しないこともあるかもしれませんね。そんなとき、誰かにお話を聞いてもらいたいと感じたら、それはとても自然な気持ちです。そんな状況では、専門の機関に相談することも大切な選択肢になります。
次のような場所で、あなたのお話を丁寧に聞いてもらえるかもしれません。
- 職場の産業医やカウンセラー
- 地域の保健センター
- 精神保健福祉センター
また、心療内科や精神科を訪ねることに抵抗があるかもしれませんが、専門家のサポートを受けることで、あなたに合ったアドバイスや治療を見つけられる可能性が広がります。ほんの少しの勇気で、きっと助けになる一歩を踏み出せるはずです。
誰しも、一人ですべてを抱え込む必要はありません。時には、専門家の力を借りてみてはいかがでしょうか。全てを一度に解決する必要はなく、一歩ずつ進むことも大切です。あなた自身の心を大切にしながら、少しずつ進んでいきましょう。
働き方を見直すヒント:がんばりすぎない働き方とは


もしセルフケアをしても、「どうしても今の職場ではがんばりすぎてしまう…」と感じているなら、それは「働き方」を見直す時かもしれませんね。心と体が健康で、長く介護のお仕事を続けていくためには、自分に合ったペースで働くことがとても大切です。
自分を責めることなく、少しだけ立ち止まって考えてみるのもいいかもしれません。そんな時にできることとして、以下のことを試してみてはいかがでしょうか。
- ご自身の気持ちを整理する時間を作る
- 働く時間や環境について、可能な範囲で調整を試みる
- 同僚や上司、ご家族に気持ちを共有してみる
全てを完璧にしようとしなくても大丈夫です。一歩一歩、小さな実践から始めてみてくださいね。そして、ご自身の健康が何よりも大切であることを忘れないでください。
自分のペースで働ける介護派遣や単発のメリット
「正社員として働くのが普通だ」と思っている方も多いかもしれませんが、実はもっと柔軟で自分らしい働き方が存在します。例えば「介護派遣」や「単発(スポット)」の働き方です。正社員だと、シフト調整が難しかったり、委員会活動や残業、人間関係の悩みに苦しむことがあるかもしれませんね。しかし、派遣という選択肢は、自分のペースを大切にしたい方にとって、多くのメリットがあります。
週3日だけ働く、午前中だけ働く、自宅から30分以内の施設がいい、など自分のライフスタイルに合わせた働き方が選べます。これにより、プライベートの時間を作りやすく、心身ともにリフレッシュしやすくなります。
契約に基づいて働くため、基本的にサービス残業はありません。業務範囲も明確なので、無理に仕事を抱え込む必要がありません。
職場の人間関係に悩んだときは、契約が終了すれば新しい職場へ移ることができます。これにより、気苦労を軽減し、仕事に集中しやすくなります。



「でも、派遣は不安定じゃない?」
「給料が少なくなるのでは?」
と心配になるかもしれません。しかし、最近の介護業界では人手不足が深刻で、派遣スタッフの需要は高まっており、好条件の求人も増えています。たとえば、介護士向けの人材派遣サービス「レバウェル介護派遣」では、時給1,700円以上の高時給の求人が豊富にあります。「給料日まで待たなくちゃ…」という方にとっては、効率的に収入をアップさせるチャンスですし、急な出費にも安心な給料前払いサービスも利用できます。
自分らしい働き方を見つけることは、自分を大切にすることにつながります。もし今の働き方に少しでも疑問を感じている方は、新しい選択肢として派遣を検討してみるのはいかがでしょうか。「全部やらなくていい」「一歩ずつでいい」という心のゆとりを忘れずに、あなたらしいペースで進んでみてくださいね。
職場のサポートを上手に活用する
働きすぎないスタイルを手に入れるためには、自分一人で頑張り続けるのではなく、周囲のサポートを上手に取り入れることが大切です。正社員の場合は上司や同僚、派遣社員の場合は派遣会社の担当者が、あなたの力強い味方となってくれることでしょう。
派遣会社は、単にお仕事を紹介するだけではありません。働き始めた後も、さまざまなサポートを通じてあなたを支えてくれます。例えば、【レバウェル介護 派遣】では、就業後のフォローがとても充実しています。職場で気になることや、直接言いにくい悩みがあれば、専任の担当者がいつでも相談に乗ってくれます。そして、職場との調整を担ってくれるので、ひとりで問題を抱える必要はありません。
さらに、地域に根ざした専門のコンサルタントがあなたの希望やスキルを丁寧に聞き取り、無理な提案をせずに本当に合った職場を見つけ出すお手伝いをしてくれます。このようなサポートは、「派遣は初めてで不安…」という方や、資格や経験がない方にとっても、安心して次の一歩を踏み出す大きな助けとなるでしょう。
がんばりすぎないためには、頼れる存在を見つけることが重要です。信頼できる派遣会社のサポートを活用することで、心のゆとりを持ちながら、自分らしく介護のお仕事と向き合うことができるようになるはずです。
- 周囲のサポートを積極的に活用する
- 専任担当者に気軽に相談する
- 自分にぴったりの職場を皆で見つける
- 「一歩ずつ」でいいと心に留める
信頼できるサポートの存在が、あなたの負担を軽くし、自信を持って働くための心強い味方になります。
まとめ
ここまで、介護の仕事をされている皆さんが「がんばりすぎ」に陥りやすいサインやリスク、そして心と体を守るためのセルフケアの重要性、新しい働き方についてお話ししてきました。介護というお仕事は、本当に尊く、やりがいのあるものです。ですから、自分を犠牲にすることなく、長く続けていただきたいと心から願っています。
「少しがんばりすぎているかも」と感じる瞬間があるとしたら、それはあなたが真剣に、誠実に向き合っている証です。どうか自分を責めることなく、まずはその努力を認め、ねぎらってあげてください。もし、今の働き方に限界を感じているなら、勇気を持って環境を変えることも考えてみませんか。派遣という働き方は、あなたに余裕をもたらし、心と時間を大切にしながら介護の仕事を続けるための賢い選択肢の一つです。
「次の給料日までどのくらいかな…」とカレンダーを眺める日々から、「もっと自分の時間を大切にしたい」という願いを叶える日々へと変わることができるかもしれません。少しの変化で、日々が楽になるのなら、新しいことを試してみる価値はあると思います。
あなたの希望を丁寧に伺い、無理に求人を勧めることはしません。専任のコンサルタントが、あなたが「自分らしい働き方」を見つけるお手伝いを全力でいたします。「ちょっと話を聞いてみたい」「どんな求人があるのか知りたい」そんな気軽なお問い合わせも大歓迎です。あなたの心と体が壊れてしまう前に、一度ご相談いただければと思います。
- 自分を責めないで、むしろ認め合いましょう
- 環境を変える勇気を持つことも選択肢です
- 自分の時間を大切にすることで、心に余裕が生まれます
私たちは、あなたが「自分らしい働き方」を見つけるお手伝いをします。まずはご相談だけでも、お気軽にご連絡ください。あなたが笑顔で、健やかに介護のお仕事を続けられることを心から応援しています。
このブログを書いている「まきこむ」と申します。
介護支援専門員(ケアマネジャー)として働きながら、趣味で創作活動も楽しんでいます。
介護にまつわる悩みや、日々の気づき、そして「やさしい未来を一緒に歩むためのヒント」を、このブログにそっと詰め込んでいます。
読んでくださった方の心が、少しでも軽くなるように。そんな思いを込めて、言葉を紡いでいます。
どうぞ、ゆっくりと遊びにきてくださいね。













コメント