私は、現場の介護職の皆さんと一緒に、ご利用者やそのご家族のサポートを全力で行っているケアマネジャーです。介護の現場は毎日新しい発見に満ちており、学びが尽きませんね。その中でも特に気になるのが、「後輩や新人の育成」に関わることではないでしょうか。

「一生懸命に教えているのに、どうして伝わらないんだろう」
「何度も同じことを伝えているのに、なかなかできるようにならない」
と悩んでしまうこともあるかもしれません。つい自分の指導力に自信をなくしたり、相手との関係に疲れてしまったりすることもありますよね。
そんな時こそ、どうか一人で抱え込まないでほしいのです。育成がうまくいかないと感じるのは、あなただけではありませんよ。それは決して「失敗」ではなく、あなた自身や相手、そしてチーム全体が成長するための大切なサインなのです。
この記事では、育成でのつまずきを「失敗」ととらえず、関係を再び築くためのチャンスとして活かすヒントをお伝えします。少し肩の力を抜いて、一緒に考えてみませんか。
- 何度も同じことを伝える必要がある時は、自分の伝え方を振り返ってみましょう。
- 指導の場面では、焦らず、相手のペースを尊重することを大切に。
- うまくいかないと感じたときには、周りの意見を聞いてみるのも一つの方法です。
- 時には休息を取り入れて、自分の心をリフレッシュすることも忘れないでくださいね。
すべてを完璧にしようとしなくて大丈夫です。小さな一歩を積み重ねていくだけで、十分価値がありますよ。
育成の「失敗」と感じるその前に


日々一生懸命取り組んでいるのに、自分の思いがうまく伝わらないと感じるとき、少し心が疲れてしまうこともありますよね。



「また同じミスが起きたな…」
「どうして思い出してもらえないんだろう…」
と、育成が思うように進まず、ついイライラしたり、落ち込んだりすることもあるでしょう。そのようなお気持ち、私も本当によくわかります。
でも、どうかご自身を責めないでください。そして「教え方が悪かったのかな」「相手にやる気がないのかも」とすぐに結論を出す前に、少しだけ立ち止まって考えてみませんか。育成が思うように進まない原因は、きっと一人のせいではありません。
ここで、日々の取り組みに少しでも安心感を持ってもらえるよう、シンプルで実践的なヒントをいくつかご紹介します。
- ゆっくりと、相手のペースに合わせて進む
- 小さな成功を一緒に喜ぶ
- 相手の努力に感謝の気持ちを伝える
全部を完全にやりきる必要はありません。できる範囲で、一つずつ試してみるだけでいいのです。自分自身と相手を大切にしながら、少しずつ進んでいけると良いですね。
育成がつまずくのはなぜか
介護現場での育成には、いくつかの複雑な要因が絡んでいることをまず理解することが大切です。例えば、価値観や経験の違いがあります。ベテラン職員にとっては当たり前と思っていることが、新人職員には全く通じないこともあります。このようなギャップは、世代による違いだけでなく、異業種から来た方の考え方や常識の違いにも影響されます。
また、慢性的な人手不足と忙しい業務も育成の難しさを増しています。じっくり時間をかけて教えたい場面でも、「とにかくやってみよう!」と実践せざるを得ないことが少なくありません。教える側も自分の業務に追われてしまい、丁寧にフィードバックする余裕が持てず、教わる側も質問するタイミングを逃してしまうことがあります。その結果、コミュニケーションが不足し、誤解やすれ違いが育成の障害になることも。
さらに、育成方法にも改善の余地があります。介護のプロであっても、教えることのプロではありません。自分の経験に基づいた教え方が、相手に合うとは限らないのです。相手の理解度や性格を見極めずに情報を伝えると、相手が混乱したり自信をなくしたりします。育成がうまくいかない背景には、こうした多くの要因があることを知っておくことが重要です。
- 一度にすべてを完璧にしようとせず、一歩ずつ進めてみましょう
- お互いのやり方や価値観を尊重し合いましょう
- 質問のタイミングが大切です。遠慮せずに声をかけてみてください
「全部やらなくても大丈夫」「一歩ずつでいいんです」と、肩の力を抜いて取り組んでいきましょう。
「教える側」も「教わる側」も人間だから
育成において最も大切なことは、「教える側」と「教わる側」の両方が、感情を持った一人の人間であるという理解です。私たちはみんなロボットではありません。その日の体調や生活の様々な出来事によって、パフォーマンスは日々変わりますよね。
教える立場の方は、「早く一人前になって、チームの力になってほしい」という期待や責任感から、焦ることもあるかもしれません。その焦りが言葉遣いに影響を与えたり、ついキツい態度を取ってしまうこともあるでしょう。また、自分の教え方に不安を感じ、自信を無くしてしまうこともあると思います。
反対に、教わる側も不安や緊張を感じながら日々を過ごしています。「失敗したらどうしよう」「迷惑をかけたくない」という気持ちから、分からないことを「分かりました」と言ってしまったり、質問することをためらうことがあるかもしれません。特に、職場の雰囲気が緊張したり、指導者が忙しそうにしていたりすると、その傾向が強まることがありますね。
大切なことは、お互いが「完璧ではない」ということを認め合うことです。完璧な指導者も、新人もいないのですから、つまずくことがあって当たり前です。「失敗」と感じることも、相手を責めるのではなく、自分を責めるのでもなく、「なぜうまくいかなかったのだろう?」と現象自体に目を向け、一緒に考えることで、関係性を再構築する一歩を踏み出すことができます。
- 自分が完璧である必要はないと認識する
- 相手に対しても完璧を求めすぎない
- お互いに質問しやすい環境を作る
- 「失敗」を「学びの機会」と捉える
- 毎日一つ、小さな成功を見つけてみる
すべてを一度に行う必要はありません。一つだけでも試してみて、日々の中で少しずつ実践してみてください。
関係性を見つめ直す第一歩
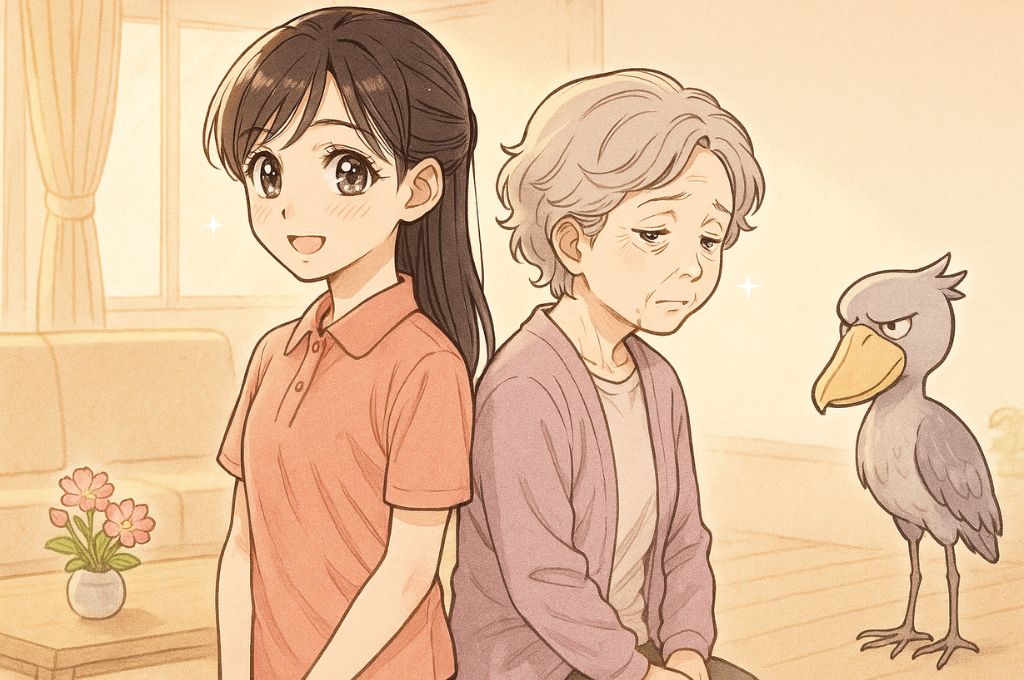
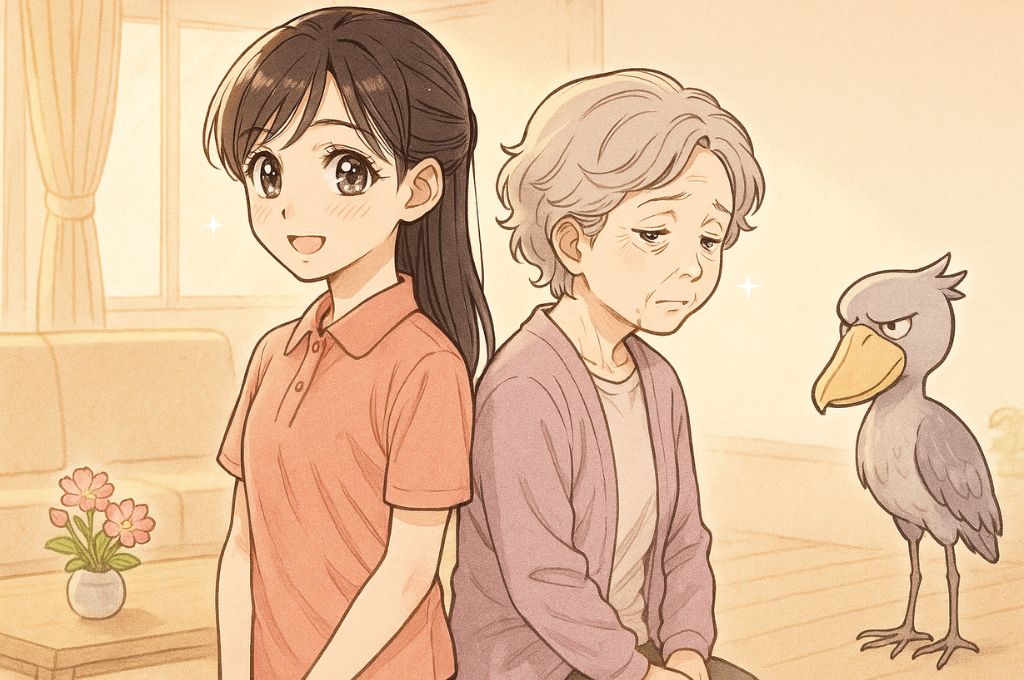
気持ちがすれ違っていると感じるとき、それは決して誰かのせいではないんですよね。そんなときは、お互いをもう一度大切に見つめ直す時間が必要なのかもしれません。
人を育てる過程での課題を乗り越えるためには、技術や知識を伝える前に、まずは「信頼関係」を築くことが大切です。信頼があれば、少し厳しい指摘も素直に受け入れられ、それが成長の糧となります。そして、教わる側も安心して質問や相談ができるでしょう。
もし今、少し関係がぎくしゃくしていると感じているなら、一度立ち止まって、相手との関係そのものを考えてみてください。
- お互いの良いところを見つけてみる
- 心から話を聞く時間を作る
- 感謝の気持ちを言葉にする
すべてを完璧にする必要はありません。少しだけでも、できることから始めてみましょう。あなたの優しさと気づかいが関係をさらに良くしてくれるはずです。
相手の視点に立ってみる
私たちはつい、「自分の常識」や「自分のやり方」で物事を判断しがちです。でも、「なぜ、こうしないんだろう?」と感じたら、その瞬間が相手の視点に立ってみるチャンスかもしれません。
まずは、相手の背景を少し想像してみましょう。例えば、その人にとって介護の仕事は初めてなのか、他の施設での経験があるのか。以前の職場ではどんな仕事をしていたのか、プライベートではどんなことに興味があるのか。そんな背景に思いを巡らせると、その人がどんな理由でそのようにふるまうのか理解のヒントになることがあります。接客業の経験が豊富な方なら、ご利用者さまとのコミュニケーションは得意でも、記録業務のような事務作業は苦手かもしれませんね。
指導する際には、その作業が「なぜ必要なのか」、「どんな意味があるのか」を丁寧にお伝えすると、相手も理解が深まります。「これをこうやって」といった指示のみだと応用が難しいことがあります。目的をしっかりと伝えることで、相手は自分で考えて行動する力をつけ、仕事への意欲も向上します。
また、「ここまでで何か分からないことはありますか?」と確認する時間を設けることも大切です。一方的に話すのではなく、相手と双方向のコミュニケーションを心がけると、相手も「自分のことを気にかけてくれているんだ」と感じて、心を開いてくれます。
- 相手の背景を想像してみる
- 作業の目的や理由を伝える
- 理解度の確認をこまめに行う
- 双方向のコミュニケーションを心がける
すべてを完璧にする必要はありません。ほんの一歩ずつ、できることから始めてみましょう。この一歩が、きっと安心感につながるはずです。
コミュニケーションの質を高めるヒント
良好な関係は、毎日の小さなコミュニケーションから生まれます。忙しい中でも、少し意識するだけでその質を大きく変えることができます。
「なんでやらないの?」という相手を責める言葉よりも、「こうしてくれると私は助かるな」というように、自分を主語にして気持ちを伝えましょう。同じ内容でも、受け取る印象は全然違います。
私たちはついミスに目が行きがちですが、相手の成長や良いところを見つけて伝えてみてください。「〇〇さんへの声かけ、すごく優しくて良かったよ」「記録のスピードが早くなったね」など、小さなことでも承認されると自信とやる気が湧いてきます。
「ありがとう」「助かったよ」の一言があるだけで、職場の雰囲気はぐっと温かくなります。忙しいときこそ、意識して伝えてみてください。
育成はスキルを教えるだけでなく、一人の人間として相手を尊重し、信頼関係を築いていくプロセスです。焦らず、少しずつ、自分らしい方法で関係を育んでいきましょう。「全部やらなくていい、一歩だけでいい」—そんな余白を大切にしながら進めていきましょう。
学び直しを成長の機会に
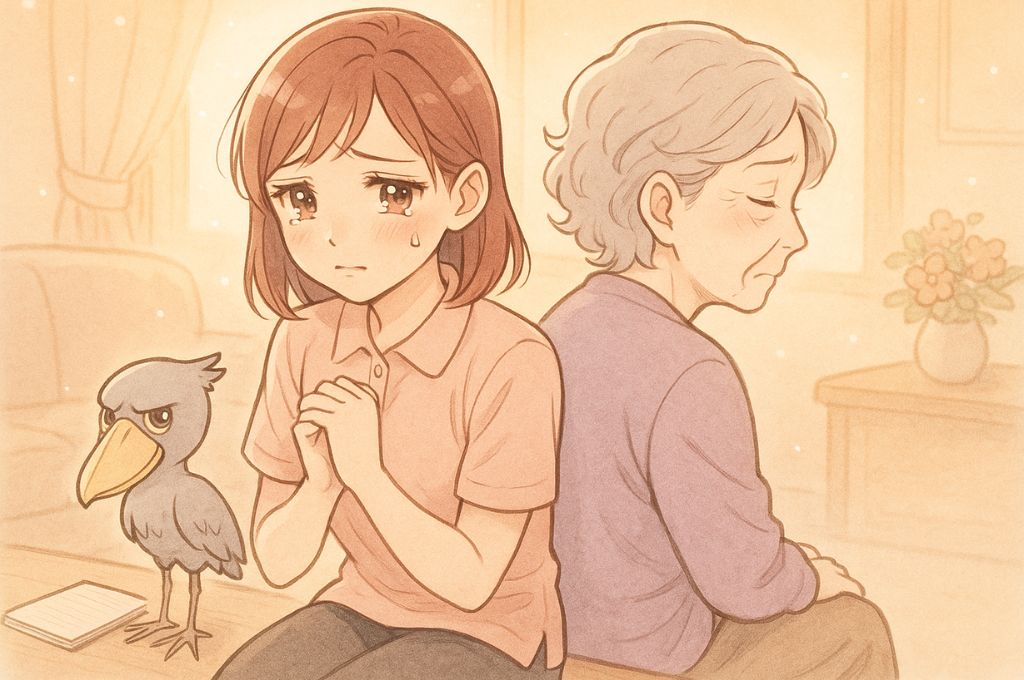
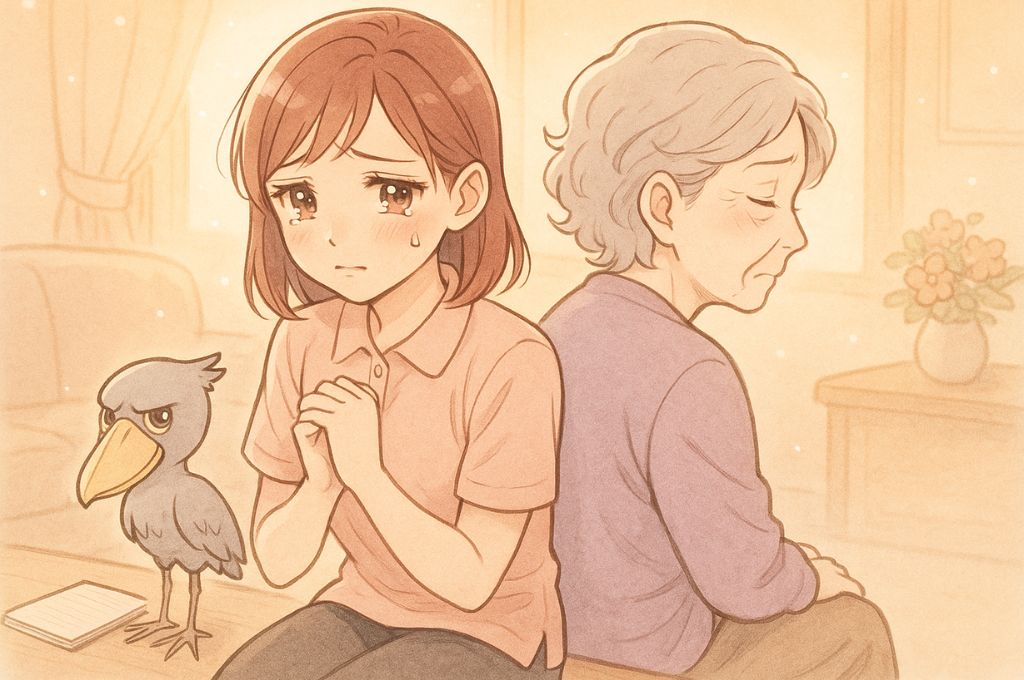
日々の生活の中で、ふと「もっと知りたい」と思う瞬間は少なくありませんよね。その気持ちは、新しい自分を発見する大切なきっかけになります。
育成がうまくいかないと感じた時、その思いは教える側にとっても貴重な「学び直しのチャンス」です。自分の指導方法や持っている知識、またご高齢者へのケアに対する姿勢を見つめ直すことで、指導者として、そして一人の介護のプロとして、さらに成長できます。
- 自分の指導方法を振り返ってみる
- 新たな知識を少しずつ取り入れてみる
- ご高齢者やご利用者の声に耳を傾ける
すべてを完璧にこなす必要はありません。一歩ずつ、自分のペースで進めることが大切です。どんな小さな一歩でも、それが未来への大きな一歩に繋がるはずです。
過去の経験から得られる教訓
若い頃は「見て覚える」が当たり前だったかもしれません。そして、少しの失敗ではくじけなかったという思い出もおありでしょう。これまで積み重ねてきた経験は、あなたの大切な財産です。それでも時には、その経験が新しいものを受け入れる壁となることもありますね。
育成の中で行き詰まりを感じたなら、それは「自分の方法は本当に最適なのか?」と考え直す良いタイミングです。過去の育成での課題や失敗を思い出してみてください。「もっと相手の話を聞けたら良かった」「つい感情的になってしまったけれど、冷静に話すべきだった」など、振り返ること自体が学びです。失敗は恥ずかしいものではなく、逆にそこから何も学ばない方が、成長の機会を逃してしまいます。
また、過去の成功に固執していないか、一度立ち止まって考えてみましょう。かつてうまくいった方法が、別の人にも同様に通じるとは限りません。人それぞれ、個性や物事の受け止め方は違います。大切なのは、その人に合ったアプローチを考える柔軟性です。
過去の経験を豊富に持つ一方で、新しい方法を常に模索してください。それが指導者としてのあなた自身も成長させてくれるはずです。
- まずは小さなことから始めてみてください。
- 全てを完璧にする必要はありません、一歩を踏み出すだけで十分です。
- 相手の話をじっくりと聞く機会を作ってみましょう。
- 自分の感情を整理した上で、冷静に伝える練習をしてみるのも良いでしょう。
それぞれの出会いが成長につながる一歩ですので、焦らずゆっくりと進めてください。
新しい知識やスキルを取り入れる方法
介護の世界は、制度の変化や新しいケア技術、認知症ケアの考え方などが常に進化しています。あなたの知識は、最新のものでしょうか?過去の経験に基づく指導が、新人職員を混乱させることもあれば、ケアの質にも影響を与えることがあります。ですから、今持っている知識を振り返ることも大切です。
- 事業所内の研修に参加する
- 外部のセミナーや勉強会に出てみる
- 他の事業所の職員と交流して、新しい視点を得る
- 介護福祉士やケアマネジャーといった資格取得を目指す
さらに、新人職員から学ぶという姿勢も忘れないでください。彼らの新鮮な視点や、異なる分野でのスキルは、現場の課題を解決するヒントになることもあります。「こういうやり方もあるんだ」「その考え方は面白いね」といった気持ちで、互いに学び合うことで、信頼関係を築くことができます。
大切なのは、信頼される指導者になるために、学び続ける姿勢を持つことです。でも、すべてを一度にやろうとしなくても大丈夫です。小さな一歩を踏み出すことで、新しい気づきや安心感を得られるはずです。
働き方の多様性がもたらす再構築のチャンス
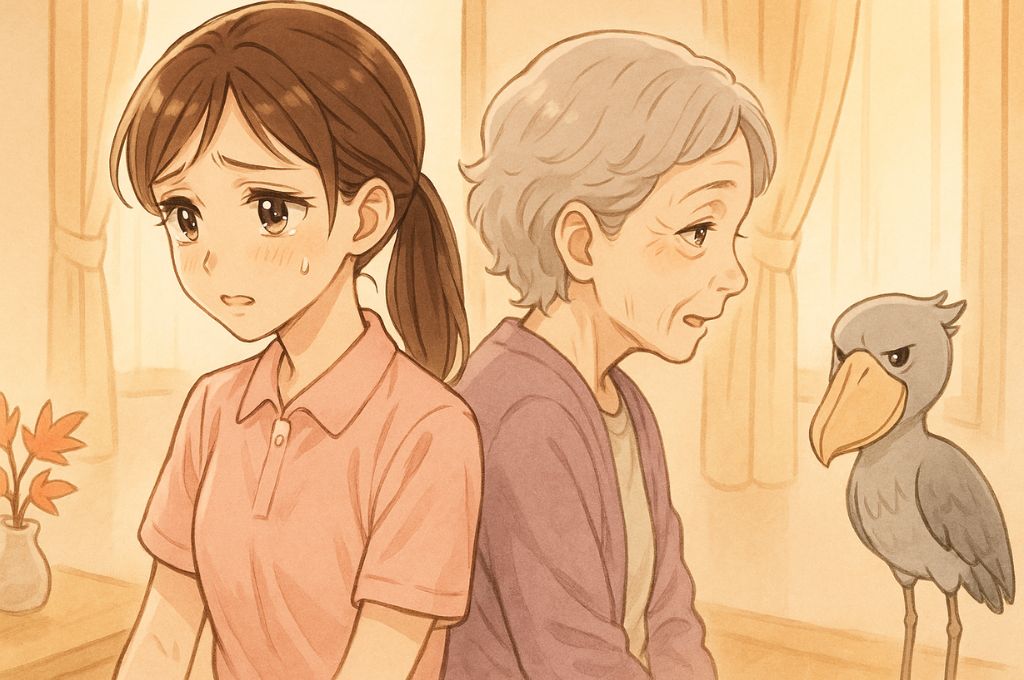
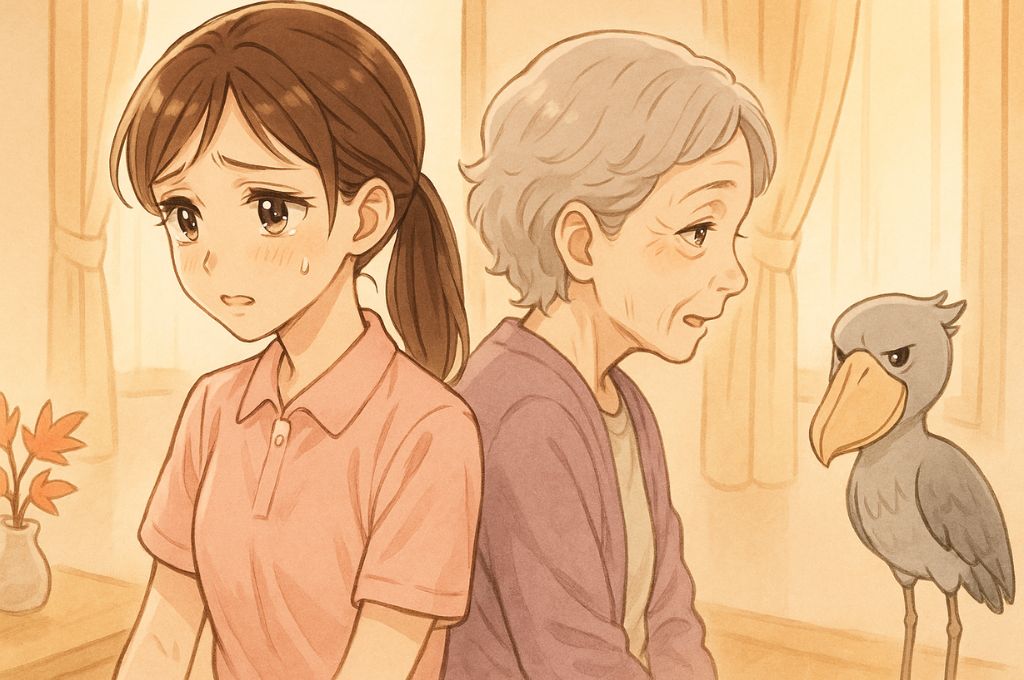
「こんな働き方もあるんだ」と気づく時って、まるで窮屈だった世界が少し広がるような感覚ですよね。その小さな気づきが、新しい可能性への扉をそっと開けてくれることがあります。
もし、育成や人間関係に疲れ、仕事への意欲が下がってしまったと感じる時があったら、少しだけ環境を変えてみることも考えてみてください。一つの場所で長く働くことは素晴らしいことですが、時には物理的に距離を置くことで新たに見えてくる景色もあるものです。
今は働き方が多様化している時代ですから、自分にぴったりの場所でまた輝けるチャンスがきっと見つかります。
- 一度にすべてを変える必要はありません。小さな一歩から始めるだけで大丈夫です。
- 自分の気持ちをまず大切にし、自己批判を手放してみましょう。
- 休息を取って心と身体をリセットする時間を意識しましょう。
ほんの少しの変化が、あなたの新たな一歩を後押しするかもしれません。それぞれのペースで、一つずつ試してみてくださいね。
派遣や短期・単発の働き方で得られる視点
正社員として同じ職場で長く働いていると、どうしても視野が狭くなってしまうことがありますよね。「この施設のやり方が当たり前」と思い込み、他の可能性を見逃してしまうかもしれません。そんな時に、派遣や短期・単発といった働き方が、新しい風を運んでくれることがあります。
派遣という選択肢の魅力は、いろいろな職場を経験できるところです。異なるタイプの施設や理念に触れることで、「こんなケアの方法もあるのか」「こういった指導の仕方もあるんだ」と、日々新しい発見があるでしょう。多様な価値観に触れることで、あなたの介護への考え方がより豊かで柔軟なものになっていきます。
また、育成のプレッシャーから解放される時間も持てます。派遣スタッフとして現場に入ると、自分の業務に集中することができ、新しい視点で「教わる側」に立つことができます。その経験は、新人の不安や、喜ばれる言葉を改めて理解するきっかけになるかもしれません。そして、将来誰かを指導する立場になった時には、必ず大きな力になるでしょう。
そして、時には人間関係をリセットしたい、心身をリフレッシュしたいと思うこともありますよね。そんな時こそ、派遣という働き方が自分を再構築するための効果的な手段となることでしょう。
- 一度に全てを変えようとしないで、一歩ずつ進めること
- いろいろな施設での経験を通じて、自分に合ったスタイルを発見する
- 他者の視点に触れて、新しい考え方に柔軟になる
どれもすぐに実践する必要はありません。ゆっくりと、あなたのペースで進めていきましょう。
介護のプロとして成長し続けるために
介護のお仕事を長く、健康的に続けていくためには、何よりもまず「自分に合った働き方」を見つけることが大切です。給与や勤務時間、職場の人間関係、キャリアの向上など、重視するポイントは人それぞれですよね。他の人にとっての「良い職場」が、あなたにとっても必ずしもそうとは限りません。
時には立ち止まって、「自分はどんな働き方をしたいのだろう?」と考える時間を持ってみてください。育成に悩んだ経験は、指導者としての成長につながり、人間関係の悩みは、チームワークの重要性を再認識させてくれます。また、環境を変える決断は、新たな視野を広げ、可能性を引き出してくれるものです。
働き方も、正社員やパート、派遣、短期・単発などいろいろあります。介護士の派遣・求人なら!【レバウェル介護 派遣】それぞれにメリットとデメリットがありますので、特徴を理解し、ライフステージや目標に合わせた選択をしてみてください。一つに固執するのではなく、常に自分をアップデートする柔軟さが、これからの介護のプロに求められる力かもしれません。
あなたらしいキャリアを、あなた自身の手で少しずつ築いていってくださいね。焦らず、できることから始めてみましょう。大切なのは一歩を踏み出すことです。あなたのペースで進んでみてください。
- 自分が大切にしたいことを紙に書き出す
- 定期的に自分の働き方を見直す時間を持つ
- 別の選択肢にも目を向けてみる
- 小さな変化から始めて、無理をしない
無理せず、ゆっくりで大丈夫ですよ。
まとめ
介護の育成において「うまくいかない」と感じることがあるかもしれません。でも、それは決してあなたの指導力が足りないからではありません。教える側と教わる側、どちらの感情や背景、そして忙しい職場環境など、様々な要因が絡み合っているのです。このような時には、誰かを責めるのではなく、「何が原因で難しくなっているのか」を見つめ直しましょう。そして、相手の立場に立つことで、より良いコミュニケーションが生まれます。
育成に悩む経験は、あなたが指導者として、さらには介護のプロとして成長するチャンスです。過去の経験を振り返り、新しい知識を得る「学び直し」の姿勢を忘れずに。
もし、今の職場での人間関係や働き方に疲れを感じたら、思い切って環境を変えるのも一つの手です。派遣などの新しい働き方を試みることでリフレッシュされ、新たな視点を得られるでしょう。
介護の仕事は、ご高齢者と深く関わる大変やりがいのある素晴らしい仕事です。一人で悩まずに、周りの仲間や外部のサービスを頼りにしながら、あなたらしく輝ける場所を見つけてください。心よりあなたを応援しています。
- 原因を冷静に見直す
- 相手の視点で考える
- 小さな学び直しを大切にする
全部を完璧にこなす必要はありません。まずは一歩から始めてみてくださいね。
このブログを書いている「まきこむ」と申します。
介護支援専門員(ケアマネジャー)として働きながら、趣味で創作活動も楽しんでいます。
介護にまつわる悩みや、日々の気づき、そして「やさしい未来を一緒に歩むためのヒント」を、このブログにそっと詰め込んでいます。
読んでくださった方の心が、少しでも軽くなるように。そんな思いを込めて、言葉を紡いでいます。
どうぞ、ゆっくりと遊びにきてくださいね。













コメント