介護職の新人が早期離職する現状と背景
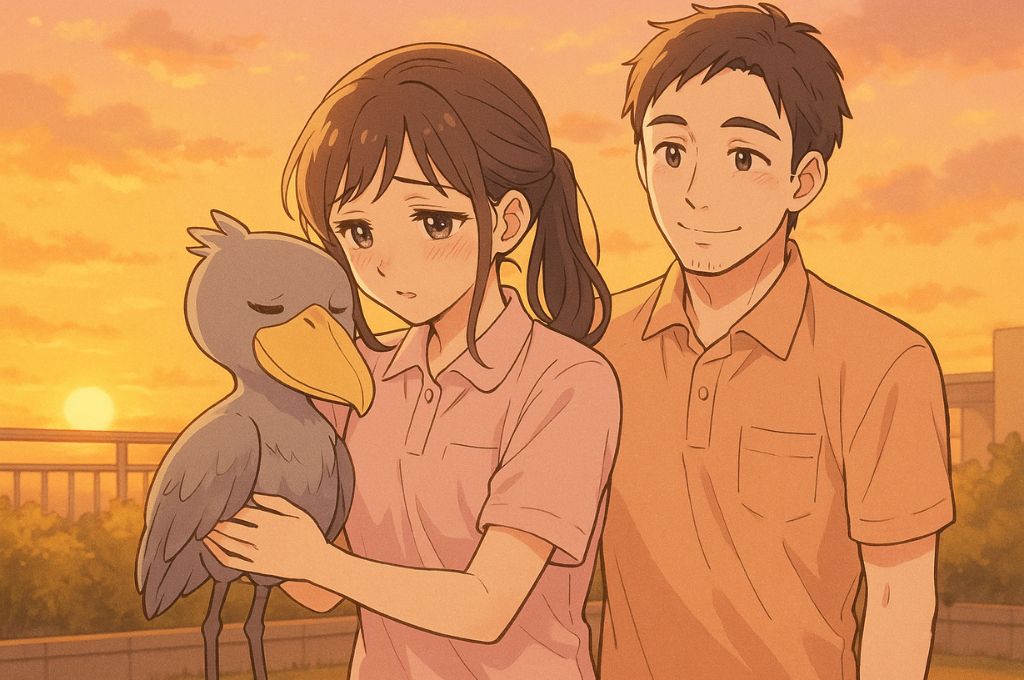
介護の道を歩むことを決意し、希望を胸に抱いて働き始めた新人の方々が、その過程で心が折れてしまうことがあります。私たちは、そんな彼らの声にならない声に、そっと耳を傾けてみることが大切です。介護業界は、社会にとってなくてはならない重要なお仕事であるにもかかわらず、離職率の高さが長年の課題となっています。厚生労働省の調査によれば、介護職の離職率は他の産業と比較して高い水準にあり、特に採用後1年未満で離職するケースが多いのが実情です。これは介護職に限らず、病院から在宅や施設に活躍の場を移した理学療法士や作業療法士、言語聴覚士といったリハビリ専門職でも同様の傾向がみられます。
なぜ、希望に満ちて入職した彼らが短期間で現場を去らざるを得ないのでしょうか。そこには、個々の事情や理想と現実のギャップがあることと思います。しかし、多くの離職者が口にする理由として、職場の人間関係や業務の負担、そして「思っていたように教えてもらえなかった」という教育への不満が挙げられています。この「教えてもらえなかった」という声の背後には、もっと深刻で根深い問題が潜んでいることもあります。
私たちケアマネージャーが様々な事業所を訪れる中で感じるのは、新人の方々が職場で孤立してしまい、誰にも相談できずに、一人で悩み疲弊している姿です。そんな時、彼らが自分を責めすぎないように、一歩ずつ進むための小さなヒントをご紹介します。
- 職場でのちょっとした会話を大切にする
- 疑問に思ったことは小さなことでも周りに聞いてみる
- 辛いと感じたときは、まずは深呼吸をしてみる
すべてを完璧にこなす必要はありません。一歩ずつゆっくりと進んでいけばいいのです。そして、何よりも大切なのは、あなた自身がどう感じているのかを大切にすることです。私たちはあなたの心に寄り添い、共に歩んでいきたいと願っています。
「指導不足」と片付けられない理由
新人の方が職場を去ってしまったとき、「あの指導者がもっと丁寧に教えていれば…」と思うこともあるかもしれません。でも、ちょっと待ってくださいね。この考え方だけでは、大切なことを見逃してしまうかもしれません。
実は、「指導がうまくいかない」という状況は、指導者一人の問題ではなく、組織全体の課題が背景にあることが多いのです。
慢性的に人手が足りない現場では、指導役の方も自分の仕事に追われ、新しく入った方とじっくり向き合う余裕がないことがよくあります。実地で学ぶとはいえ、「見て覚えて」という方法になりがちです。でもこれは、決して指導者の怠慢ではなく、やむを得ない状況もあるのです。結局、組織として統一された教育プログラムがなければ、指導が個人任せになってしまい、新人の方が混乱することも。
また、ご高齢者のケアにおけるリハビリ職の方も、明確な指針がない中で「どう動けばいいんだろう?」と迷ってしまうことがあります。
こんなふうに、「指導不足」の陰には、組織全体の課題があることが多いのです。だから、もしあなたがそうした状況に不安を感じているなら、自分を責めないでくださいね。大切なのは、みんなで少しずつ工夫をし、できる範囲での改善を試みることです。
- 一度に全部やらなくて大丈夫。まずは小さなステップを。
- 自分ができることを一つだけ、やってみましょう。
- チームで話し合う時間を少しでも持てると何かが変わるかもしれません。
焦らず、無理をせずに取り組んでいけば、少しずつ良い方向に進めるはずです。あなたのペースで、一歩ずつ進んでいきましょう。
新人介護職の離職を招く組織の課題
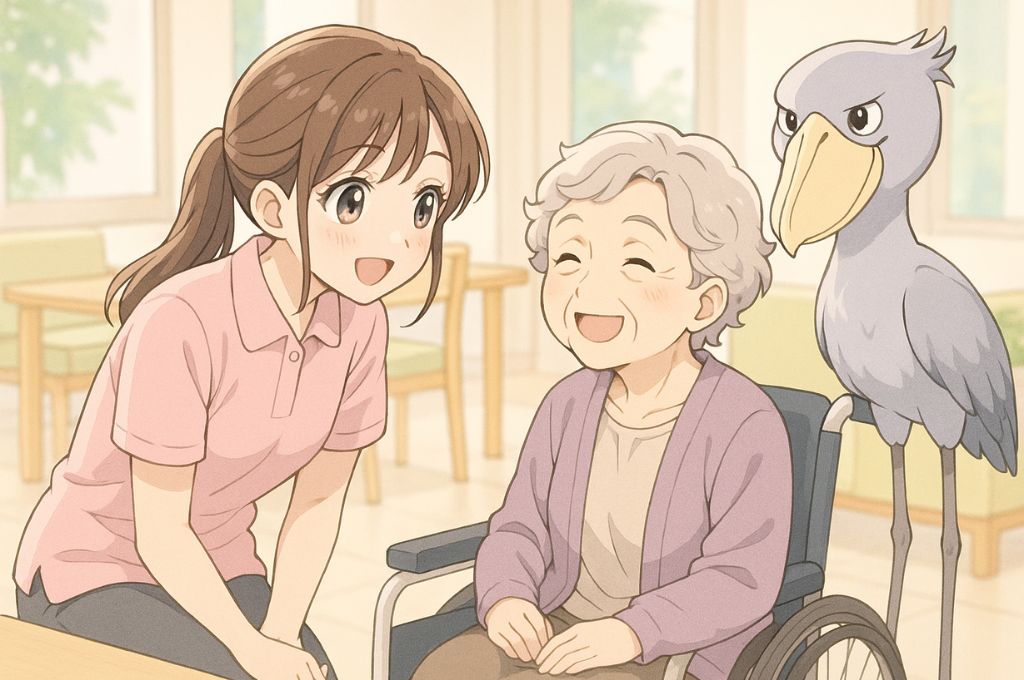
せっかく一生懸命に育てた新人が、早々に辞めてしまうことがあると、本当に切ない気持ちになりますよね。その背景には、その人自身の問題ではなく、もしかしたら私たちの組織の仕組みに根ざした何かがあるのかもしれません。
新人の方が心を閉ざし、退職という決断をするまでには、さまざまな組織的な要因が関わっています。ここでは、特に離職のきっかけとなりやすい組織の課題について、4つの視点から考えてみましょう。
- 日々の会話が新人の言葉を引き出せていますか?
- 上下関係に限らず、オープンな場を設けることを大切に。
- 新人の成長を見守る環境がありますか?
- 小さくても具体的な達成目標を立て、それを一緒に振り返る場を作りましょう。
- 働く環境が心地よくなっていますか?
- 休息の取り方や働き方に柔軟性を持たせることを心掛けて。
- フィードバックが新人の自信を育んでいますか?
- ポジティブな面を意識して伝え、一歩ずつ成長を実感できるように。
実践する際は「全部を完璧に」ではなく、小さな一歩から始めてみてください。きっとそれが、良い変化を生むきっかけになります。読んでいただいたあなたが少しでも気が楽になり、新たな気づきを得られることを願っています。
不適切な人員配置と業務量
介護の現場において、深刻な人手不足に直面している方々は多いのではないでしょうか。日々、職場での業務が多く、一人ひとりが時間に追われる状況にあります。こうした環境では、新人をじっくりと育てるのが難しくなってしまいますよね。
本来でしたら、新人の方々には数ヶ月間マンツーマンの指導が理想ですが、現実には難しいことも多いです。指導役の方も多くのご利用者を担当し、日々の業務に追われてしまいがちです。
結果として、新人の方は充分なサポートを受けられず、現場に立たされてしまうことも。質問したくても忙しそうな先輩方を見てためらってしまうこと、ありますよね。そのような日々の小さな不安や疑問は、どうしても蓄積してしまいます。
PT、OT、STといった専門職の方々も、専門的な業務に集中したくても介護業務に追われ、「本来の役割とは…」と悩むことがあるかもしれません。
このような状況で、新人の学びの機会が減ってしまうのは残念なことです。しかし、それが早期離職につながることを防ぐためのヒントを少しご紹介します。
- 忙しい時も、一度立ち止まって「自分ができる小さな一歩」を考えてみる
- 「全部こなさなくてもいい」と、少し力を抜いてみる
- 難しいと感じたら、上司や同僚に小さな相談をしてみる
- 一度に多くを学ぶのではなく、毎日一つでも新しいことを覚える
こうした小さな実践が、きっと明日につながります。自分を責めるのではなく、一歩一歩を大切にしてみてくださいね。
組織内のコミュニケーション不足
「報・連・相(報告・連絡・相談)」は、介護現場でチームとしてケアを行う際に、安全と質を確保するために欠かせない要素です。このコミュニケーションがうまく機能していない職場では、新人の定着が難しいこともあります。例えば、朝の申し送りで大切な情報が共有されず、ご利用者の状態変化に新人が気づけない場合、対応が遅れてしまいます。チームカンファレンスが形だけのものになってしまい、職種間の意見交換が活発でないと、新人はチームの一員としての実感を得られず、孤独感を深めてしまいます。
特に、介護士、看護師、そしてPT、OT、STといった多職種が連携する現場では、質の高いコミュニケーションがケアの質に直結します。専門職がアセスメントしたご利用者の心身機能に関する情報が介護士に正しく伝わらなければ、リハビリの効果も日常生活で活かされません。逆に、介護士が気づいたご利用者の日々の細かな変化が専門職に共有されなければ、リハビリ計画を見直すことも難しいです。このような情報不足は、単なる業務上のミスを引き起こすだけでなく、職員間の信頼関係を損ね、職場全体の雰囲気を悪化させます。新人が安心して「相談」できる環境のない職場では、小さなミスが大きな事故につながるリスクも高まり、新人は萎縮し、働く意欲をなくしてしまいます。
- 情報共有の場では、大切なポイントを明確に伝える
- 新人がお互いに質問しやすい環境を作る
- 定期的なフィードバックを心がける
- 少しずつ、無理せずに一つひとつ実践してみる
「すべてを完璧にしないといけない」と思わず、一歩ずつでも進んでいければ、それだけで大きな前進です。あなたが安心して働ける、そんな職場づくりを一緒に目指していきましょう。
評価制度やキャリアパスの不明確さ
どんな方でも、自分の努力が認められたり、成長を実感できたり、将来に希望を持つことで仕事に対するモチベーションを保つことができますよね。しかし、介護業界では、評価制度やキャリアパスがはっきりしていない職場が多いことも事実です。「頑張ってもお給料は変わらない」「この先どんなスキルを身につければいいのだろう」といった不安が、新人さんの離職理由になることも少なくありません。
たとえば、毎日まじめに業務に取り組み、自己研鑽を続けても、それがどのように評価されるのかわからなければ、頑張る意味が感じられなくなることもありますよね。また、介護福祉士やケアマネージャーを目指すにしても、組織としてサポートしてくれる制度がなければ、一人で乗り越えるのは難しいものです。これは、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士の方にも当てはまるお話しです。
専門職としての成長にはっきりとした道筋が示されていないと、不安になるのは自然なことです。明るい将来を具体的に思い描ける職場は、やはり魅力的に見えますよね。ですから、明確な目標やそのための道筋、努力を正しく評価する仕組みといったサポートが重要です。もし今の状況に不安を感じていたら、まずは以下の小さな実践を試してみてください。
- 自分の成長を振り返る時間を持つ
- 将来やりたいことを少しずつリストアップ
- 職場で信頼できる人と相談する
ハラスメントや人間関係の問題
介護の現場で働く皆さまへ。介護労働安定センターの調査によると、職場を離れる理由として、「人間関係の問題」が常に上位に挙げられています。中には、新人に対するいじめやパワーハラスメント、「お局」問題といった厳しい現実がある場合もあります。こうした環境で、ミスをしつこく責められたり、無視されたりすると、新人の方々は深く傷ついてしまいます。本来、チームとしてお互いを支え合うべき場でこのような問題が起こるのは、本当に辛いことです。
問題は、これらのハラスメントだけではありません。それを目の当たりにしながら見過ごしたり、「新人だから仕方ない」といった誤った思い込みで容認してしまう組織の体質にもあります。例えば、管理者が問題を認知しながら適切に対応できない場合や、相談窓口がうまく機能しない場合、被害を受けた方々は「ここでは自分が守られない」と感じ、退職を考えてしまうのです。この人間関係の悩みは、介護士の方々だけでなく、PT、OT、STの方々にも非常に深刻です。専門職としての意見が「生意気」と取られたり、既存の職員の中に入れなかったりすることで、孤立を感じることもあるでしょう。
そこで、職員一人ひとりが安心して働き、尊重される心理的安全性が、新人が職場に定着するために大切です。その実現に向けて、小さな一歩を踏み出しましょう。全部を完璧にする必要はありません。以下は日々の業務の中で、少しずつ取り入れられるヒントです。
- 他の人の意見を尊重し、話をじっくり聞く時間を持つ
- 困っている同僚に声をかけ、小さな助けを惜しまない
- 相談窓口を活用し、問題を一緒に解決する姿勢を大切にする
ご高齢者の皆さまやご利用者の方々に対するサービスを最高のものにするため、職場環境の改善に向け、一緒に取り組んでいきましょう。すべてを完璧にする必要はありません。最初の一歩を踏み出すこと、それが未来への大きな力になります。
組織全体で新人介護職を育てる視点

「新人さんにしっかり教えなければ」と、一人で抱え込んでいませんか?実は、新人さんの成長は、チーム全体で喜びを分かち合う大切な瞬間かもしれません。
では、新人さんが辞めずに安心して働き続けられる職場を作るには、どんなことができるでしょうか?大切なのは、「指導を一人に任せる」のではなく、「組織全体で新人さんを育てる」という考え方を持つことです。
新人さんの意見やアイデアを歓迎し、いつでも質問できる雰囲気を作ります。
新人さんが成し遂げたことをチーム全員で共有し、みんなで喜びを感じます。
新人さんに教えることで、逆に自分たちも多くのことを学べるという心持ちで臨みます。
歓迎とサポートの文化を醸成する
新人さんが初めて職場に足を踏み入れたときの印象は、これからの居心地に大きな影響を与えるものですよね。そのため、「あなたを歓迎していますよ」という気持ちを、組織全体でしっかりと伝えることが大切です。例えば、さりげなく用意されたウェルカムボードや、朝礼での紹介など、小さな工夫が新人さんの心を和らげてくれます。「何か困ったことがあったら、指導担当の〇〇さんだけでなく、誰にでも気軽に声をかけてくださいね」という一言があるだけでも、新人さんの心理的な負担はかなり軽くなることでしょう。
また、お昼ご飯に誘ったり、休憩時間にちょっとお話をしたりと、業務以外のコミュニケーションも忘れずに。これらは、新人さんを「ただ教えるべき存在」としてではなく、「一緒に働く仲間」として受け入れる姿勢の表れです。
このような歓迎とサポートの文化は、一人だけの力では築けません。管理者やベテラン職員、中堅そして少し先輩の皆さん全員が、心を込めて新人さんを迎えようとする共通の気持ちを持つことで、組織の文化として根付いていくのです。
- 簡単なウェルカムボードを作る
- 朝礼での温かい紹介
- 「何かあったら気軽に話しかけてね」の一言
- ランチや休憩時間に声をかける
適切なOJTと継続的なフィードバック
新人の方が安心して業務に取り組めるように、OJTの方法も少し工夫してみましょう。「見て覚えろ」という形だけでは、慣れない環境で不安を感じることも多いと思います。そこで、体系的で計画的なOJTプログラムが役立ちます。
- 新人の成長をサポートするために、教育担当の方や部署全体で「○○までに何ができるようになる」という具体的な目標を設定し、チェックリストを作成しましょう。
- 先輩社員であるプリセプターが、新人の方に寄り添いながらマンツーマンで指導にあたります。
- 定期的に短い面談を設けて、進捗を確認し、新人の悩みや質問に耳を傾けます。
フィードバックも重要です。新人が何かできるようになったら、「〇〇ができるようになったんですね、すごいですね!」と伝え、次の目標に一緒に挑戦する提案をしてみましょう。こうしたフィードバックで、新人の方も自身の成長を実感しやすくなり、モチベーションを保つことができます。
特にPT、OT、STの方には、それぞれの専門領域に詳しい先輩が指導者になると良いでしょう。組織としても、指導役の業務量を調整し、教育に専念できる環境を整えることが大切です。
一度にすべてを完璧にしようとせず、小さな一歩を大事にしながら進めていきましょう。それがきっと、新人の方にも安心感を与えることになります。
メンター制度や相談窓口の設置
仕事の中で、日々の業務を指導してくださる「プリセプター」とは別に、心のサポートをしてくれる「メンター」がいることはとても大切です。メンターは、年齢の近い先輩や他部署で働く職員など、直接の利害関係がない「斜めの関係」を持つ方が理想的です。仕事や人間関係、プライベートな悩みなど、プリセプターや上司には話しにくいことも安心して相談できる相手がいると、本当に心が軽くなりますよね。
メンターとの定期的な面談は、新人の方が一人で悩みを抱え込まないための重要な仕組みです。ただ、組織内での人間関係に悩む場合、内部の人に相談しづらいこともあるでしょう。そんな時のために、ハラスメントなどに関する外部の相談窓口(EAP:従業員支援プログラムなど)を設置し、職員の皆さまに知っていただくことも大事です。このように、さまざまな角度からサポートを整えることで、「この職場は自分を大切に思ってくれている」と安心でき、それが長く働ける基盤になります。
- メンターは「斜めの関係」の人が理想
- 定期的にメンターと面談を設定
- 外部相談窓口を設置・周知
- 全部やらなくていい、まずは一歩から
あなたが今できる小さな一歩を大事にしてくださいね。すべてを完璧にする必要はなく、少しずつ前に進めることが何よりです。
キャリア形成を支援する仕組み作り
新人の方が「この職場でずっと働きたい」と感じるためには、自分の将来のキャリアをはっきりと描けることが大切ですね。職場として、皆さんのスキル向上やキャリアアップを支援する心構えを持つことが重要です。例えば、介護福祉士やケアマネージャーの資格取得を目指す方には、受験費用の一部を支援したり、試験前に利用できる休暇制度を設けることが考えられます。
さらに、内部での研修を充実させるだけではなく、外部の研修やセミナーへの参加を促し、その費用を法人が負担する制度を導入することも効果的です。これは、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士といった専門職にとって、特に魅力的に映るかもしれません。学会への参加支援や、専門資格取得に向けたサポートは、専門性を高める大きな助けとなります。
また、年に一度のキャリア面談を通じて、職員一人ひとりが将来どんな専門性を身に付けたいか、どんな役割を果たしていきたいかを共有し合い、組織としてその実現をどうサポートできるかを一緒に考える機会を作ることも大事です。
こうした取り組みは、職員の皆さんの働く意欲や組織への貢献意識を高めることにつながります。
- 資格試験のための費用支援を検討する
- 試験前に使える休暇制度を導入する
- 外部研修やセミナー費用を法人が負担する制度を設ける
- 年に一度、キャリア面談を実施する
全てを一度に始める必要はありません。小さな一歩からで十分です。あなたがお仕事に励む姿勢が職場の雰囲気をより良いものにします。
全員で作り上げる働きやすい職場環境
新人が職場に長く留まるかどうかは、その職場がどれだけ「働きやすい環境」であるかが大きな鍵を握っています。この「働きやすさ」を築くのは、決して一人の力だけではありません。みんなで協力し、少しずつ作り上げていくものです。
例えば、みんなで協力して残業を減らすための工夫を考えてみたり、ICTの導入や業務分担の見直しを行ったりすることが考えられます。さらに、仲間同士でお互いの仕事をカバーし合い、有給休暇を取りやすい雰囲気を作ることも、大切な一歩です。「ありがとう」や「助かります」といったポジティブな言葉が自然と飛び交う職場だと素敵ですね。
こういった基本的なことを一人一人が「自分のこと」として捉え、少しずつ実践していけると良いのではないでしょうか。管理者の方々は、職員の声にしっかりと耳を傾け、現場からの改善提案を歓迎する姿勢を大切にしてください。
「働きやすい職場」は新人にとってだけでなく、そこにいる全ての職員にとってプラスになるものです。職員の満足度が上がると、ケアの質も高まり、ご利用者やそのご家族の信頼とつながるという良いサイクルが生まれます。新人の方が安心して働ける環境を作ることは、結果として組織全体の成長や発展にもつながる大切な取り組みです。
- 業務を見直し、無理なくできる工夫を少し試してみましょう。
- ポジティブな言葉を普段の会話に少し取り入れてみませんか?
- 自分にできる範囲で、お互いのサポートを心がけてみましょう。
まとめ
今回は、介護の現場で働く新人の方々が早期に離職してしまう背景について、そしてそれをどう防ぐかに焦点を当てたお話をしました。「指導が悪い」という個人の問題として片付けてしまうと、本当の問題は見えてきません。新人さんが定着しにくい裏には、人員配置やコミュニケーション、評価制度、人間関係など、組織全体で解決すべき深い問題が隠れています。
新人の方を「未来の大切な仲間」として温かく迎え、チーム全体で育て上げる文化を作り出すことが大切です。そして、職員一人ひとりが安心して働け、やりがいを持ち続けられる環境作りを皆で進めていくこと。これこそが、新人の定着率を高め、介護サービスの質を向上させるための確かな道だと私は信じています。
もしこの記事をご覧になって「今の職場では成長が見込めないかも」と感じたら、一度立ち止まって自分のキャリアを考え直してみるのも良いかもしれません。新しい環境に身を置くことで、皆さんの可能性が大きく広がることもあります。大切なのは、一人で抱え込まず、信頼できる人に相談することです。

「今の働き方、本当に満足していますか?」
この記事を読んで、キャリアについて考え始めた方もおられるでしょう。私たちは、理学療法士(PT)、作業療法士(OT)、言語聴覚士(ST)などの専門職の方々や、介護現場を支える介護士の方々が「自分らしい働き方」を見つけられるようお手伝いします。



「夜勤のない職場で、プライベートを充実させたい」
「子育てと両立できる、単発や派遣の仕事を探している」
「PT、OT、STとしての専門スキルを活かせる職場に出会いたい
こんな思いがある方の力になります。豊富な求人情報の中から、皆さんのライフスタイルやキャリアプランに合う職場を一緒に探しましょう。
面談で緊張することが不安な方もいらっしゃるかもしれませんが、ご安心ください。まずは皆さんの希望や不安を丁寧に伺い、親身になってサポートいたします。皆さんのキャリアの可能性をもっと広げてみませんか?
お気軽に、あなたのお話を聞かせてください。お待ちしています。
このブログを書いている「まきこむ」と申します。
介護支援専門員(ケアマネジャー)として働きながら、趣味で創作活動も楽しんでいます。
介護にまつわる悩みや、日々の気づき、そして「やさしい未来を一緒に歩むためのヒント」を、このブログにそっと詰め込んでいます。
読んでくださった方の心が、少しでも軽くなるように。そんな思いを込めて、言葉を紡いでいます。
どうぞ、ゆっくりと遊びにきてくださいね。













コメント