介護の現場に飛び込んで間もない頃。
ご利用者のケアに向き合いながら、ふと「自分には向いていないのかもしれない」と感じたことはありませんか?
慣れない業務、知らない専門用語、緊張する人間関係――
夜勤の疲れがたまった日に、思わず涙がこぼれそうになる瞬間もあるかもしれません。
でも、それはあなたが真剣に向き合っている証。
「できない」と感じるのは、何もしていないからではなく、ちゃんと“やろう”としているからなんです。
この記事では、介護職1年目でよくある悩みや戸惑いにそっと寄り添い、
自分を責めすぎずに乗り越えるためのヒントをお伝えします。
- 「向いていないかも…」という気持ちの正体とは?
- よくある“1年目の壁”とその乗り越え方
- 気持ちを整理するための簡単な実践法
焦らなくて大丈夫。
いまの揺らぎは、あなたらしいケアを育てていくための“はじまり”です。
これから介護の仕事を始めたい方も、もっと自分に合った職場を探したい方も、条件からしっかり比較できると安心ですよね。
介護士の求人、募集は【レバウェル介護】勤務地・給与・働き方など、あなたに合った条件をもとに探せるので、無理なく続けられる環境が見つかりやすいです。
はじめに|「向いてないかも」の気持ちに寄り添って
介護職として働きはじめた最初の数か月は、生活も心も大きく揺れる時期。
仕事や家事と両立しながら勉強するのは大変。でも、ポイントをおさえた教材があれば時間を有効に使えます。
介護福祉士の国家試験に合格するならこのテキスト1冊だけで大丈夫!【受かるんです】“今年こそ合格したい” その気持ちを後押ししてくれるのが、この一冊です。
ご利用者への声かけひとつ、移乗介助の動作ひとつに、毎日神経をすり減らしていませんか?

「いつも笑顔でいなきゃ」
「失敗は許されない」
そんなふうに、気づかぬうちに自分を追い込んでしまうこともあるかもしれません。
でも――
その苦しさは、あなたが手を抜かずに真剣に向き合っているからこそ生まれるもの。



「私、向いてないのかな…」
と感じる気持ちは、頑張っている証なのです。
まずは、その声にそっと耳を傾けてみましょう。
それは「やめたい」のサインではなく、ここからどう進もうかと考える準備のサインかもしれません。
この先のページでは、小さな一歩を踏み出すための視点や実践のヒントをお届けします。
ひとつでも心に残る言葉が見つかれば嬉しいです。
1年目の壁とは|なぜ誰もがつまずくのか
「1年目の壁」という言葉を聞いたことはありますか?
これは介護職に限らず、多くの新人が経験する“心と体のバランスが崩れやすい時期”のことです。
慣れない業務、職場の空気感、ご利用者との距離のとり方。
すべてが新しく、気づかないうちに心も体もフル稼働になっています。
- 「仕事に慣れなきゃ」と無理をして笑顔をつくる
- 先輩の言葉ひとつに一喜一憂する
- 休日も頭の中は現場のことでいっぱいになる
こうした負荷が少しずつ積み重なり、「もう無理かも」と感じる瞬間が訪れやすくなるのです。
でもそれは、あなたが仕事に真剣だからこそ起こる自然な反応。
つまずくのは、歩き始めた証です。
誰もが通る道だと知るだけで、心が少し軽くなるかもしれません。
環境・人間関係・ケアの重圧が重なる時期
介護職1年目は、まるで“すべてが初めて”の連続。
身体的な疲れと、心の緊張が重なりやすい時期でもあります。
- 施設内の動線や備品の位置を覚えるだけで精一杯
- 夜勤やシフト勤務で生活リズムが乱れ、疲れが抜けにくい
- 先輩やご利用者との会話にも気を張り、常に緊張状態
- 目の前のケアが“命や暮らし”に直結していることへの責任感
これらの要素が同時に押し寄せることで、「自分は向いていないのかも…」という不安が芽生えやすくなります。
でも、それは“あなたがちゃんと向き合っている証”でもあるのです。
大切なのは、立ち止まる勇気と、少し肩の力を抜くこと。
今のしんどさも、通りすぎていく過程のひとつです。
真面目な人ほど「できない自分」に苦しむ
一生懸命な人ほど、自分の失敗や不器用さに敏感です。
少しのミスでも「私は向いていないのかも…」と心を痛めてしまうことがあります。
- 完璧にやろうとするあまり、少しのミスでも自己評価が下がる
- うまくいかなかった場面を何度も思い返してしまい、次に踏み出しづらくなる
- 周囲からの言葉を「期待」ではなく「重圧」と感じてしまい、心が苦しくなる
でも、このつまずきは“あなたが真剣に向き合っている証”です。
誰にでもある通過点だからこそ、大切なのは《放置しないこと》。
小さな成功や「うまくできたかも」という感覚を、ひとつずつ積み重ねていきましょう。
その歩みこそが、あなたのケアスタイルを育てていきます。
その気持ちは“サイン”です|弱さではなく、大切な気づき



「向いていないのかもしれない…」
そんな気持ちがふと湧いてきたとき、それはあなたの心からの大切なメッセージです。
「もっと無理なく、安心して働きたい」という《サイン》かもしれません。
たとえば、こんな状態が続いていませんか?
- 些細なミスに何度も落ち込んでしまう
- 休日でも頭の中が仕事のことでいっぱい
- 疲れが取れず、眠りも浅く感じる
もしひとつでも当てはまるなら、一度立ち止まり、体調や気持ちをメモしてみましょう。
《“いまの自分”に気づくこと》が、次のケアへの第一歩になります。
- 1分間の深呼吸で「マイクロ休憩」を
- 信頼できる先輩や同期に、ちょっとだけ気持ちを打ち明ける
- 好きな香りやハーブティーで、リラックスタイムをつくる
こうした小さなケアを重ねることで、心のコンディションを自分で整える力が育っていきます。
それは、決して“弱さ”ではなく、《自分を守る力》です。
「向いてない」は心の悲鳴かもしれない
介護の現場で感じるプレッシャーは、
ときに「向いていないのかも…」という思いに姿を変えて、心の奥から聞こえてきます。
その声は、あなたの“がんばりすぎ”に気づいてほしいという《心のサイン》かもしれません。
こんな兆しが続いていたら、少し立ち止まってみましょう。
- 業務日誌の記録が重たく感じ、「どうせうまくできない」と思ってしまう
- 疲れが抜けず、食欲や睡眠リズムに乱れが出てきた
- 人と話すのが億劫になり、1人で抱え込む時間が増えている
こうした状態は、“怠け”ではなく、心のブレーキがかかっている証です。
まずは、スマホのメモや小さなノートに《今日の気持ち》《体の状態》を書き留めてみてください。
仕事や家事と両立しながら勉強するのは大変。でも、ポイントをおさえた教材があれば時間を有効に使えます。
介護福祉士の国家試験に合格するならこのテキスト1冊だけで大丈夫!【受かるんです】“今年こそ合格したい” その気持ちを後押ししてくれるのが、この一冊です。
たった数行でも、自分の状態を“見える化”することは、ストレスを整えるきっかけになります。
「休むこと」や「誰かに頼ること」は、前を向くための準備。
あなたのペースで、自分を守るケアをはじめていきましょう。
比べず、今の自分を見つめてみる
同期や先輩と比べては落ち込んでしまう――
そんな瞬間、ありませんか?
でも、誰かと比べて自信をなくすのは、あなたが真面目に向き合っている証拠です。
大切なのは、「誰かより上手に」ではなく、「昨日の自分よりちょっとでも前へ」進んでいるかどうか。
以下の小さな工夫を取り入れて、少しずつ“自分だけの歩幅”に気づいていきましょう。
- 《今日の“できたこと”》を3つだけ書き出す(どんなに小さくてもOK)
- 「比べてるかも」と感じた瞬間をチェックリストにして見える化
- 朝の準備中や移動中に、1分だけ目を閉じて深呼吸
他人のペースではなく、自分のペースで育てた“できた”は、
やがてあなたの《確かな自信》に育っていきます。
今日のあなたにできたことは、きっと昨日の自分を超えています。
その小さな一歩を、どうか忘れずに。
先輩たちも通った道|“壁”の向こうにあったこと



「自分だけがつまずいている気がする」
そんなふうに感じてしまうときこそ、思い出してほしいことがあります。
今は頼れる存在に見える先輩たちも、かつては同じように悩み、立ち止まりながら道を探していたということ。
その“壁”の向こうで、彼らが見つけたのは——ほんの少しの工夫と、自分なりのやり方でした。
たとえば……
- 記録業務に苦しんだ先輩
利用者さんの「好みノート」を作ってみたことで、会話のきっかけが増え、記録の視点が変化。 - 夜勤に疲弊していた先輩
フローや申し送りの工夫を提案。働き方が改善され、チームからの信頼を得るように。
うまくいかなかった経験こそ、成長の“種”です。
それに気づけたとき、新しい景色が少しずつ見えてきます。
今のあなたの不安や違和感も、やがて誰かを助ける力に変わっていく。
そう信じて、一歩ずつ進んでいきましょう。
続けて気づいた「変化する視点」
慣れない業務に追われていた日々。
でも、続けていくうちに、ふと気づくことがあります。
最初は「うまくやらなきゃ」「迷惑をかけないように」と思っていたのに、
ある日、自分の視点が少しずつ変わってきたことに気づくのです。
- “与えるケア”から“受け取るケア”へ
「支える側」だと思っていた自分が、ご利用者の笑顔や言葉に救われることが増えてくる。 - 手順優先から、“その人の想い”を最優先に
手順どおりの介助ではなく、「今日はどんな気持ちかな?」と、心に目を向けるようになる。 - *報告・連絡・相談から“チームづくり”へ
一人で抱え込まず、声をかけ合いながら支え合うことで、仲間との信頼が深まっていく。
そんな変化は、ある日突然ではなく、
日々の試行錯誤の中から、少しずつ芽吹いていくもの。
視点が変わると、同じ景色がやさしく見える。
そんな瞬間を、あなた自身の中にも見つけられるはずです。
苦手だったことが、強みに変わることもある



「苦手かもしれない」
「向いていないかも」
そう感じることの中にこそ、あなただけの強みの芽が隠れているかもしれません。
- 話すのが得意じゃない…だからこそ“観察力”が光る
言葉よりも表情や仕草に敏感になり、ご利用者の小さな変化にいち早く気づけるようになる。 - 力仕事が苦手…だからこそ“工夫の介助”が身につく
無理をせず、身体の使い方や福祉用具を上手に活かして、安全なスタイルを確立できる。 - 暗記が苦手…だからこそ“自分なりの覚え方”が育つ
自作のイラストや語呂合わせが、やがて後輩への指導の力にもなっていく。
「苦手」は、劣っているという意味ではありません。
自分なりに向き合った過程そのものが、あなただけの財産になります。
その努力は、誰にも真似できない“あなたらしさ”へと変わっていきます。
向いている・向いていないより大切なこと
介護の現場では、「向いているかどうか」を気にしてしまう瞬間があります。
でも本当に大切なのは、あなたが“どんな姿勢で向き合っているか”ということ。
- ご利用者の立場で考え続けること
目線を合わせ、声のトーンを工夫しながら、相手の気持ちを想像する。 - ミスや不安をそのままにせず、誰かに頼ること
「助けてください」が言えるのは、真剣に取り組んでいる証です。 - 小さな違和感を見過ごさず、少しずつ工夫を加えていくこと
「昨日より今日」を大切にする姿勢が、信頼へとつながっていきます。
思いやりは、あなたの“技術”ではなく“在り方”そのもの。
それは、どんなに時代が変わっても、介護の現場でいちばん大切にされる力です。
仕事や家事と両立しながら勉強するのは大変。でも、ポイントをおさえた教材があれば時間を有効に使えます。
介護福祉士の国家試験に合格するならこのテキスト1冊だけで大丈夫!【受かるんです】“今年こそ合格したい” その気持ちを後押ししてくれるのが、この一冊です。
「向いている・向いていない」は、あとからついてくるもの。
今ここで、誰かのために悩みながらも動けているあなたは、すでに十分に“向いている”のです。
ケアのかたちは、人それぞれ
介護に“正解”はありません。
あなたが届けているケアは、世界にひとつだけのかたちをしています。
- にぎやかなおしゃべりで、笑顔を引き出すケア
声のトーンや表情で、場をあたためる力も立派なスキルです。 - 静かにそっと寄り添い、安心感を伝えるケア
一緒にいるだけでほっとする存在は、何よりの支えになります。 - 趣味や動線など、その人らしさに寄り添った声かけ
マニュアルでは届かない気づきを、あなたの感性が引き出しています。
“自分らしいケア”に正解も不正解もありません。
そのやり方が、たしかに誰かを支えている。
だから今日も、あなたのペースで大丈夫です。
“あなたらしさ”が届いている場面はきっとある
自分では気づけなくても、
あなたのケアが“届いている瞬間”は、きっと日々の中にあります。
- ふとしたときに見せてくれた、ご利用者さんの自然な笑顔やうなずき
- *ご家族からそっとかけられた「ありがとう」の一言
- チームの中で「〇〇さんにお願いしたい」と任された場面
それは、あなたにしかできない寄り添い方が、
誰かの心にふれている証です。
小さな出来事でも、心に残った場面をメモしてみましょう。
気づけばそれが、あなただけの“自信ノート”になります。
もう少し続けてみようかな、と思えたときに
「辞めたい気持ち」から一歩進んで、
「もう少しだけやってみようかな」と思えたとき――
その芽を、大切に育てていきましょう。
無理なく続けるためには、小さな工夫を日常に取り入れることが鍵です。
- ミニゴールを決める(例:ご利用者さんの好きな飲み物を1つ覚える)
- チェックリストやカレンダーで“できた”を見える化
- 週に一度、自分をねぎらう“ごほうびタイム”を作る
マラソンでいう「給水所」や「エネルギージェル」のように、
“休息と補給”を意識して、自分を整える時間を持つことも大切です。
がんばり続けなくていい。
少しずつで大丈夫。
あなたのペースで、一歩ずつ。
自分なりのペースと距離感で
続けていくうえで大切なのは、誰かと比べないこと。
「自分にとってちょうどいいリズム」を見つけていくことです。
こんな工夫が、“こころの揺れ”をやさしく整えてくれます。
- オン・オフの切り替え時間を意識的につくる
- がんばりすぎない、心にゆとりのある目標を立てる
- 勉強会やグループワークで、学びや負担をシェアする
- 毎朝「疲れ度」「気持ちのゆとり度」を1分だけメモする
あなたをいちばん長く支えてくれるのは、あなた自身です。
気づいてあげてください。
今日を、ちゃんと歩いている自分のこと。
無理のない「相談」や「休む選択肢」も視野に
がんばりすぎそうなときほど、ひと呼吸おいて「頼る」ことを思い出して。
- 同期や先輩に「少しだけ聞いてもいいですか?」と声をかける
- 施設の相談窓口や外部のEAP(従業員支援プログラム)を活用してみる
- 有給休暇や半休を上手に使って、心と体を休ませる
- 相談やお休みのあとは、自分の変化をそっとメモしておく
“相談すること”や“休むこと”は、サボりではありません。
それは、**より良いケアを続けていくための「あなたの大切な技術」**です。
まとめ|あなたが感じた壁は、強さの証かもしれません
「向いていないかも…」と感じたあの日。
それは、あなたが真剣に介護と向き合っている証です。
- 壁を感じたら、自分の心と体の声にそっと耳をすませる
- 比べず、今日できた小さなことを見つめてみる
- 相談することや休むことも、ケアの一部と考えてみる
- 苦手なことに工夫を重ね、あなただけの強みに育てていく
そうししずつ育まれていく“あなたらしさ”が、
ご利用者やチームを支える大きな力になります。
まだ迷いが残っていても、大丈夫。
その一歩一歩が、あなたの未来をつくっていきます。
どうか、自分にやさしく。
あなたのケアスタイルは、きっとこれからも深まっていきます。
これから介護の仕事を始めたい方も、もっと自分に合った職場を探したい方も、条件からしっかり比較できると安心ですよね。
介護士の求人、募集は【レバウェル介護】勤務地・給与・働き方など、あなたに合った条件をもとに探せるので、無理なく続けられる環境が見つかりやすいです。
このブログを書いている「まきこむ」と申します。
介護支援専門員(ケアマネジャー)として働きながら、趣味で創作活動も楽しんでいます。
介護にまつわる悩みや、日々の気づき、そして「やさしい未来を一緒に歩むためのヒント」を、このブログにそっと詰め込んでいます。
読んでくださった方の心が、少しでも軽くなるように。そんな思いを込めて、言葉を紡いでいます。
どうぞ、ゆっくりと遊びにきてくださいね。



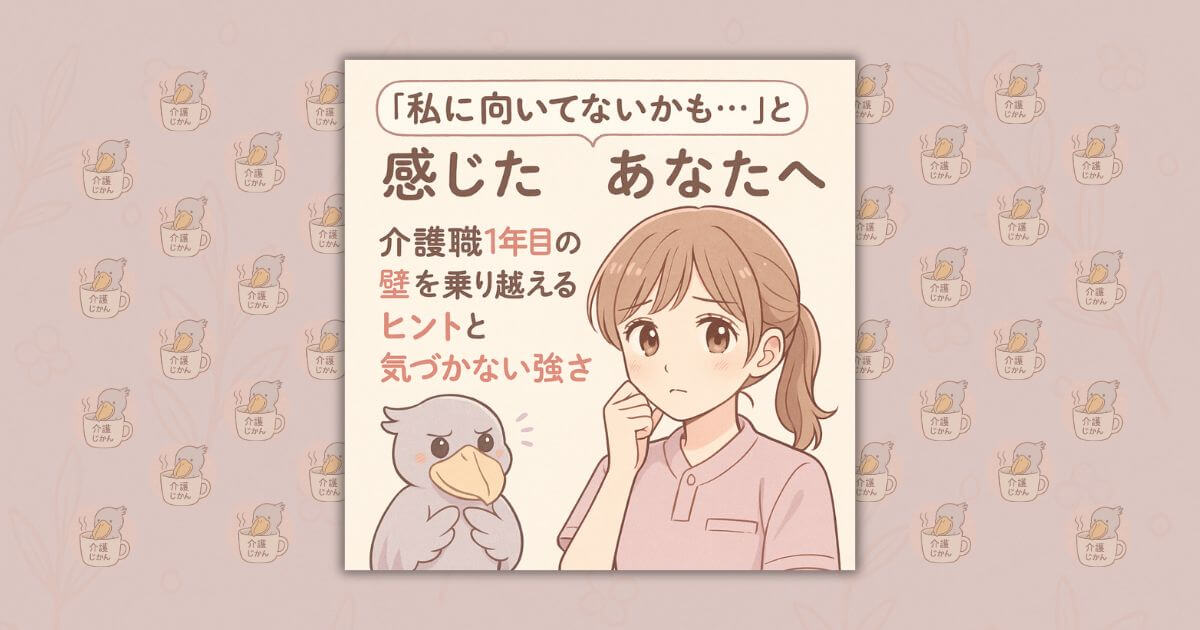









コメント