現場介護で“安心感”を生む動きの秘密|手の差し出し方・立ち位置・移乗のコツ
歩行や移乗の介助のたびに、

「なぜか怖がられてしまう」
「うまく寄り添えない気がする」
そんな戸惑いを感じたことはありませんか?
声かけの言葉やスピードに気を配っていても、
ご利用者の表情がふとこわばる瞬間。
その陰には、言葉よりも先に伝わっている“身体のメッセージ”があるのかもしれません。
本記事では、「安心感」を生み出すケアの動きを
- 手の差し出し方
- 立ち位置
- 移乗時のふるまい
この3つの視点から、やさしく紐解いていきます。
大切なのは“正しい型”ではなく、現場で試せる小さな工夫。
あなたのやさしさが、もっと自然に伝わるためのヒントを、
ご自身のリズムで取り入れてみてください。
これから介護の仕事を始めたい方も、もっと自分に合った職場を探したい方も、条件からしっかり比較できると安心ですよね。
介護士の求人、募集は【レバウェル介護】勤務地・給与・働き方など、あなたに合った条件をもとに探せるので、無理なく続けられる環境が見つかりやすいです。
なぜ「動き」が安心感につながるのか
介護の現場では、言葉を交わす前から、
私たちの“動き”が、ご利用者に無言のメッセージを届けています。
ふだんどこに立つか、どんな歩き方をしているか、
手をどう差し出すか──
そうした何気ないふるまいが、
「この人は安心できる」と感じてもらえるかどうかを左右することもあるのです。
少しだけ立ち位置を工夫する。
歩調を合わせてみる。
手を差し出すスピードをゆっくりにしてみる。
ほんの小さな動きの積み重ねが、ご利用者の不安をやわらげ、
信頼というあたたかな関係へとつながっていきます。
言葉より先に伝わる“身体のメッセージ”
ご利用者と向き合うとき、
最初に届いているのは、言葉ではなく“身体のリズム”かもしれません。
どんな動き方をしているか。どこに立つか。どんな姿勢か。
そうしたふるまい一つひとつが、ご利用者の安心感に深く関わっています。
無言のリズムが相手を迎える
ゆったりとした動きには、自然と呼吸を整える力があります。
介護職の動きが一定で落ち着いていれば、見守られる側の心拍や気持ちも穏やかに。
反対に、慌ただしい動きは緊張や不安につながることもあります。
立ち位置で示す“安心の境界線”
距離感は、思っている以上に感情に影響します。
近すぎると圧迫感に、遠すぎると孤独感に。
程よい距離でそっと見守ることで、「ここにいてくれる」という安心感が生まれます。
目線と姿勢のハーモニー
目線は水平か、少し下げるくらいがちょうどよく。
肩の力を抜き、やわらかな姿勢を意識すると、ご利用者も自然と緊張をゆるめてくれます。
上から見下ろさない、やさしい姿勢は、心のバリアをそっとほどいてくれるのです。
ご高齢者が感じる「怖さ」とは
介助の場面で、ご高齢者が表情をこわばらせるとき。
それは、言葉にされない“怖さ”を感じている瞬間かもしれません。
不安を生む背景には、こんな理由が隠れていることがあります。
- 転倒やケガへの不安
足元が不安定なまま、支えが遅れると、
「このまま倒れるかもしれない」という強い恐怖につながります。 - 自立心がくずされる感覚
「自分でやりたかったのに」「勝手に手を出された」──
そんな思いが、自尊心を静かに傷つけてしまうこともあります。 - プライバシーが守られていないと感じるとき
立ち位置が近すぎたり、触れ方が急だったりすると、
体や心が“乱暴に扱われた”ような印象を受けてしまうことがあります。
こうした“怖さ”を理解し、動きや間合いを丁寧に整えること。
それが、言葉よりも先に伝わる“安心感の土台”になります。
手の差し出し方で変わる信頼関係
介助のときに差し出す手──
それは、触れる前から「私はここにいますよ」と伝える、大切なメッセージです。
いきなり手を取るのではなく、
まずは見える位置で、ゆっくりと手を差し出すこと。
それだけで、ご利用者の中に「受け入れる準備」が生まれます。
- 手は、相手の視界に入る位置からそっと差し出す
- 急がず、相手が“触れにくる”のを待つような姿勢を意識する
- 「つかむ」ではなく「支える」「委ねてもらう」感覚で
この静かなやりとりの中に、「信頼」が育まれていきます。
手の出し方ひとつで、ご利用者の安心感は大きく変わります。
まずは“待つ手”から、始めてみませんか。
「差し出す」ではなく「差し出される」感覚に寄り添う
手を差し出すとき、大切なのは“つかむ”のではなく、
相手が「自分から差し出せる余白」を残しておくことです。
ご利用者が“自分で決めて手を伸ばす”その一瞬に、
尊厳と安心が宿ります。
そんなケアを実現するための、小さな工夫
- 急がず、待つ
声をかけるのは、呼吸をふうっと吐いたタイミングに。
その“間”が、不安をほどく扉になります。 - 手のひらを軽く開き、平行に静止する
こちらから動かずに待つことで、「支えますよ」という静かな意思表示に。 - “点”ではなく“面”で支える
手のひら全体でやさしく受け止めることで、安心感がじんわり伝わります。 - 静かなサインを添える
指先をほんの少し動かして、呼吸に寄り添うリズムを示すと、
ご利用者の心にやわらかなリードが届きます。
この“待つ”“受け止める”という無言のやりとりが、
ご利用者の表情をふっとやわらげる瞬間につながっていくのです。
立ち位置ひとつで不安が和らぐことも
言葉をかけなくても、そっと立つ位置によって
ご利用者は「気にかけてもらえている」と感じることがあります。
これから介護の仕事を始めたい方も、もっと自分に合った職場を探したい方も、条件からしっかり比較できると安心ですよね。
介護士の求人、募集は【レバウェル介護】勤務地・給与・働き方など、あなたに合った条件をもとに探せるので、無理なく続けられる環境が見つかりやすいです。
立ち位置は、介護職の“気配”が伝わる大切な要素です。
たとえば──
斜め前方や、視界に自然に入る位置に立つだけで、
ご利用者の中に「見守られている」という安心感がじんわり広がっていきます。
- 真横や真後ろよりも、視界の端に入る“斜め前”を意識する
- 声をかける前に、まず存在をそっと感じてもらう
- 動きながら立ち位置が変わるときも、ご利用者の目線を追い越さないように
- 必要以上に近づかず、“息がしやすい距離”を心がける
ほんの少しの立ち位置の違いが、ご利用者の緊張をやわらげ、
「ここにいてくれる」という安心につながることがあります。
介助の前にまず、“どこに立つか”を、そっと意識してみてください。
正面に立つvs斜めから寄る、その違い
介助の場面で、どこに立つか──
それだけで、ご利用者の感じ方が大きく変わることがあります。
正面から近づくとき、斜めから寄るとき。
それぞれにメリットと注意点があるので、場面に応じてやさしく使い分けてみましょう。
- 正面アプローチ
メリット:目線が合いやすく、声かけもしやすい
デメリット:急に目の前に立つと、圧迫感や緊張を与えてしまうことがある - 斜めアプローチ
メリット:距離感が自然で、ご利用者が安心しやすい
デメリット:身体に手が届きにくい場面では、介助しづらさがある
どちらが正解、ではなく、
ご利用者の状態やその日の様子に合わせて、やわらかく選んでみてください。
「近づき方」そのものが、やさしいケアの第一歩になるのです。
見える位置にいることで伝わる“気づいているよ”のサイン
言葉をかけなくても、そっと視界に入り続けること。
それだけで、ご利用者には「ちゃんと気づいてくれている」という安心が届くことがあります。
たとえば──
- 斜め前に立ち、ふいに振り向いたときにも目が合う位置にいる
- 頭を少し傾けて相手の視線を受け止める
- 目が合ったときに、やわらかくほほえむ
- 手のひらをゆるやかに振るなど、小さな動きで“気づいていますよ”を伝える
こうしたさりげないサインの積み重ねが、
ご利用者の無意識に「見守られている」という安心感をそっと刻んでいきます。
声をかける前から、あなたの存在は届いているのです。
移乗の瞬間に宿る“安心”のつくり方
椅子からベッドへ、ベッドから車いすへ──
移乗の場面は、ご利用者にとってもっとも緊張が高まりやすい時間です。
これから介護の仕事を始めたい方も、もっと自分に合った職場を探したい方も、条件からしっかり比較できると安心ですよね。
介護士の求人、募集は【レバウェル介護】勤務地・給与・働き方など、あなたに合った条件をもとに探せるので、無理なく続けられる環境が見つかりやすいです。
そんなときこそ、私たちの“合わせ方”が、安心感を育む鍵になります。
- 声かけのタイミングを、ご利用者の呼吸にそっと合わせる
- 一方的に「よいしょ」と動かすのではなく、「一緒に動く」意識を持つ
- ご利用者が動こうとする瞬間を、静かに待ち、しっかり支える
“支える側”と“支えられる側”ではなく、
“同じ動きを共有するパートナー”としての感覚を持つことで、
ご利用者の心と体に、自然と安心が広がっていきます。
移乗は力ではなく、呼吸と気持ちをそろえる“共同作業”。
そこに、あたたかな信頼が宿っていくのです。
移乗は声かけと呼吸のタイミングが鍵
移乗のとき、ご利用者が身構えてしまうのは、
「いつ動けばいいのかわからない」ことが多いからかもしれません。
そこで大切なのが、声かけと呼吸のタイミングをそろえることです。
- シンプルな数字のカウントでリズムを合わせる
「3、2、1」とゆっくり数えることで、ご利用者の気持ちも動きに集中しやすくなります。 - 呼吸を吐ききるタイミングで合図を出す
息をふうっと吐いたタイミングで「せーの」と伝えると、
体の力みが抜け、より自然に動くことができます。
「いきますよ」と言いながら自分だけが動いてしまうと、
ご利用者の不安が高まることもあります。
だからこそ、呼吸と声を合わせて“動きの合図”を共有することが、
安心して身をゆだねてもらうための大切なポイントになるのです。
ご本人のペースに合わせた“共同作業”としての意識
移乗の場面を、ただの「介助」にせず、
ご本人と一緒につくる“共同作業”として捉えると、安心感はぐっと高まります。
介助される側ではなく、対等なパートナーとしての関係性を意識してみてください。
信頼の輪を広げていく工夫
- 動作のプランを共有する
事前に「今からどう動くか」を一緒に確認し、見通しをもってもらいます。 - 「どう動きたいですか?」と意思をたずねる
ご本人の希望やタイミングを尊重することで、自立への支援にもつながります。 - 呼吸と動きを合わせて、同じリズムで立ち上がる
主導せず、寄り添いながら“一緒に”動くことを大切に。 - 終わったあとに感想をシェアする
「大丈夫でしたか?」「ゆっくりでしたね」など、振り返りも信頼を育てる対話になります。
こうした積み重ねが、移乗のひとときを
“儀式”のようなあたたかな安心の場に変えてくれるのです。
「ただの動作」が「安心の習慣」に変わるまで
声のかけ方、立ち位置、手の差し出し方──
ひとつひとつは小さな動きでも、そこに“安心”を届ける意識があると、
ケアの風景が少しずつ変わっていきます。
最初は「こうした方がいいかな」と、
意識的に工夫していくことになるかもしれません。
でも、その積み重ねがやがて、“無意識のやさしさ”に変わっていきます。
- 日々の声かけや動き方を、チームで振り返る
- 小さな成功や変化を共有し合う
- 「見守る」「待つ」「寄り添う」姿勢を意識的に練習する
こうしたプロセスを通じて、
「ただの動作」だったものが、自然と“安心を生む習慣”に育っていくのです。
あなたのケアが無意識に放つあたたかさは、
ご利用者の心を、今日もそっと支えています。
振り返りとチーム共有のすすめ
“安心を届けるケア”は、ひとりで背負うものではありません。
小さな気づきや工夫を、チームで分かち合うことで、
やさしさはもっと自然に、現場に広がっていきます。
忙しい日々のなかでも、こんな取り組みなら続けやすいかもしれません。
- 週に1回、15分だけの振り返りミーティング
「今日の良かった場面」「安心できた関わり方」など、感じたことをひとことずつ。 - ホワイトボードやデジタルツールで“安心のヒント”を共有
気づきを見える形で残すことで、メンバー同士の学び合いが生まれます。 - ペアレビューやロールプレイを取り入れる
実際の動きや声かけを一緒に見直すことで、「なるほど、そういう伝わり方があるんだ」と気づくきっかけに。
ひとつのやさしさが、チームの中で育ち、根づいていく。
そんな文化が、いつの間にかご利用者にとっての“安心な空気”をつくっていきます。
小さな実践が積み重なるとき



「声のかけ方を少し変えてみた」
「手を添える位置をほんの少し調整した」
そんな小さな実践も、日々積み重ねていくことで、
ご利用者に届く“安心の質”は、少しずつ確かなものになっていきます。
- 声かけの言い回しや立ち位置の工夫を、気づいたときに記録する
- 1週間、1か月、そして1年と続けていくうちに、“無意識のやさしさ”が育つ
- やがてそれがチーム全体の文化となり、新人さんへの自然な引き継ぎにもつながる
特別なことをしなくても大丈夫。
日々の関わりのなかで「ちょっと意識する」ことが、
やがて“安心感があたりまえにある職場”をつくっていきます。
これから介護の仕事を始めたい方も、もっと自分に合った職場を探したい方も、条件からしっかり比較できると安心ですよね。
介護士の求人、募集は【レバウェル介護】勤務地・給与・働き方など、あなたに合った条件をもとに探せるので、無理なく続けられる環境が見つかりやすいです。
まとめ|あなたの動きが、安心を創る
介護の現場で、あなたが毎日積み重ねている動作には、
言葉以上に深く届く“あたたかさ”があります。
立ち位置、手の差し出し方、呼吸と声かけのタイミング──
そのひとつひとつが、ご利用者にとっての「安心」の種になるのです。
大切なのは、完璧なかたちを目指すことではありません。
現場で試しながら、自分たちらしいリズムを少しずつ見つけていくこと。
そのプロセスこそが、信頼を育て、あなた自身の自信にもつながっていきます。
焦らなくて大丈夫。
あなたの手の動き、足の運び、そっとかけた声──
それらすべてが、誰かの心をやわらかく支えています。
どうか、自分の動きを信じてください。
あなたは、ちゃんと届いています。
これから介護の仕事を始めたい方も、もっと自分に合った職場を探したい方も、条件からしっかり比較できると安心ですよね。
介護士の求人、募集は【レバウェル介護】勤務地・給与・働き方など、あなたに合った条件をもとに探せるので、無理なく続けられる環境が見つかりやすいです。
このブログを書いている「まきこむ」と申します。
介護支援専門員(ケアマネジャー)として働きながら、趣味で創作活動も楽しんでいます。
介護にまつわる悩みや、日々の気づき、そして「やさしい未来を一緒に歩むためのヒント」を、このブログにそっと詰め込んでいます。
読んでくださった方の心が、少しでも軽くなるように。そんな思いを込めて、言葉を紡いでいます。
どうぞ、ゆっくりと遊びにきてくださいね。



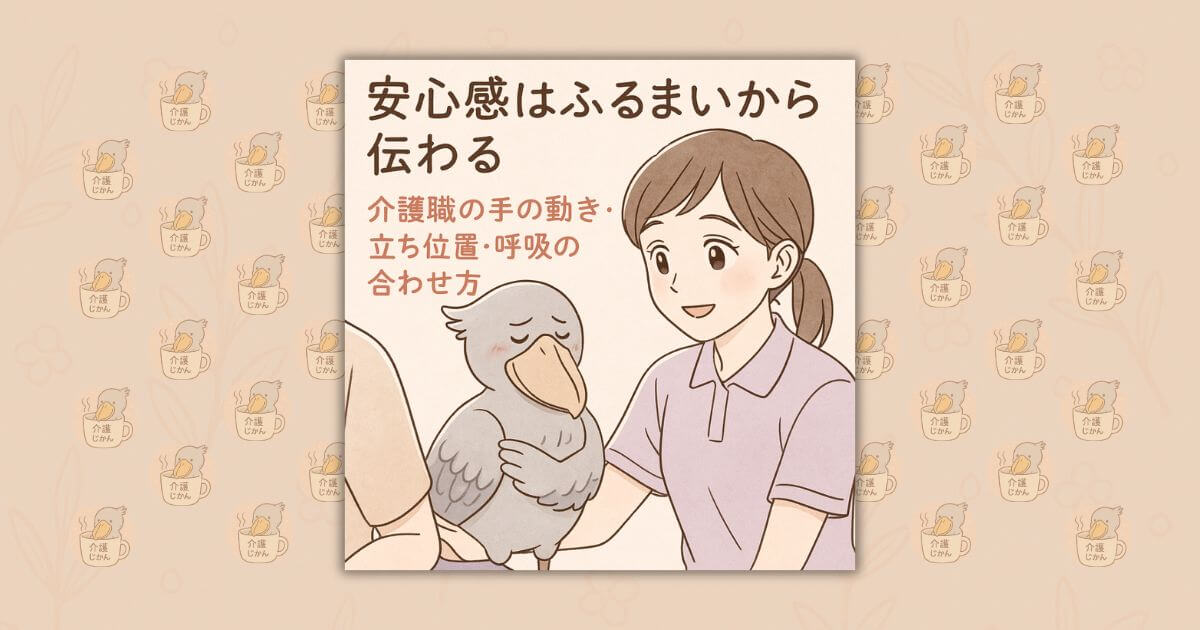



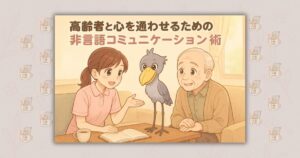
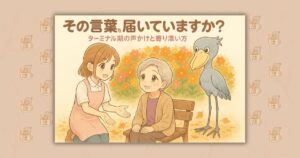


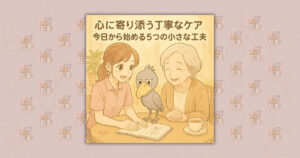

コメント