介護の現場で働く皆さん、日々の業務お疲れ様です。忙しい毎日の中で、ご高齢者一人ひとりに寄り添った記録を残すことはとても大切ですが、難しく感じることもあるかもしれませんね。ここでは、皆さんが安心して記録を続けられるようなヒントをいくつかご紹介します。
まず、何より大事なのは完璧を目指さないということです。すべてをきっちり書こうとすると負担になってしまいますから、できることから少しずつ始めてみましょう。一歩ずつ進むことで気づきを得られますし、それが次への力になります。
- ご高齢者の気持ちに寄り添い、その日感じたことを書いてみる
- 自分が記録を読む側になって、伝わるかどうかを考える
- 短くても具体的に、他のスタッフにも分かりやすい表現を心掛ける
- 疲れているときは無理をせず、今日はここまでと区切りをつける
「すべて」を目指さず「一歩」から始めてみることで、少しでも心に余裕を持って記録と向き合えますように。これが皆さんの安心や気づきにつながりますようにと願っています。
これから介護の仕事を始めたい方も、もっと自分に合った職場を探したい方も、条件からしっかり比較できると安心ですよね。
介護士の求人、募集は【レバウェル介護】勤務地・給与・働き方など、あなたに合った条件をもとに探せるので、無理なく続けられる環境が見つかりやすいです。
伝わる記録の基本を学ぶ
大切なことを伝えるための記録は、まず相手の心に寄り添う言葉から始まります。基礎をしっかりと身につけ、思いやりをもって言葉を選びながら、心を通わせる方法を一緒に模索していきましょう。
終業の頃、まだ白紙の記録を前に手が止まってしまうこと、誰しも経験がありますよね。また、申し送りで「結局どうなったの?」と聞かれて落ち込むこともあるかもしれません。でも大丈夫。大切なのは、あなたのケアを「伝わる言葉」に変換することです。基本として大事なのは、「事実」と「気づき」を分けることです。事実は、あなたが見たこと、聞いたこと、測ったこと。気づきは、そこから得られたあなたの解釈や次の行動のヒントです。読み手が同じ場面を想像できるようにするために、5W1H、主語、時制を揃えましょう。
仕事や家事と両立しながら勉強するのは大変。でも、ポイントをおさえた教材があれば時間を有効に使えます。
介護福祉士の国家試験に合格するならこのテキスト1冊だけで大丈夫!【受かるんです】“今年こそ合格したい” その気持ちを後押ししてくれるのが、この一冊です。
記録が届けられる相手を意識することも重要です。次のシフトの方々や、看護師さん、リハビリスタッフさん、ケアマネジャーさん、ご家族など、相手によって必要な情報は違いますので、その方々に合った情報を選びましょう。専門用語は避け、シンプルで分かりやすい言葉を使い、ご高齢の方々の尊厳やご家族の安心にもつながるように心がけたいですね。
- 事実と気づきを明確に分ける
- 5W1Hで具体的に書く
- 相手に合わせた情報を選ぶ
- 専門用語を避け、シンプルに表現する
「全部やらなくてもいい、一歩ずつでいい」と考えて、少しずつ実践してみてくださいね。あなたの努力は必ず誰かの役に立っていますから、自分を責めることなく進んでいきましょう。
書く意図を先に決める
記録を始める前に、まず「何を伝えたいのか」「誰に届けたいのか」をひと言で決めてみましょう。このシンプルなステップを踏むことで、記録が迷うことなく進められます。この意図が、結論を導くための“灯台”となります。
例えば、「ご利用者様の夜間の眠りの様子を共有し、夜勤での見守り方をみんなと合わせていきたい」という意図があるとします。読み手は「夜勤を担当する方々や看護スタッフ」です。そして、結論としては「覚醒の回数が減ってきて安定する傾向が見られる」と示します。
次に、事実と気づきを整理しましょう。
事実としては、「22時と2時に覚醒され、トイレへの介助が各1回必要でしたが、再度眠りにつくまでに5分しかかかりませんでした」となります。
そこからの気づきとして、「排尿後の再入眠がスムーズで、夕食後の水分量が影響しているのかもしれません」と考えられます。
このように、意図→結論→事実→気づきという順序で簡潔に記録することで、申し送りや検索の際にとても役立つかと思います。情報源や観察者、記録日も忘れずに記載するよう心がけましょう。
- 意図をしっかり持てば、記録のブレが少なくなります。
- 読んでほしい相手を明確にすると、記録がより伝わりやすくなります。
- まずは一歩ずつ、小さな実践を心がけて大丈夫です。
- 全てを完璧にこなす必要はありません。自分を責めず、少しずつ前進していきましょう。
このように一つひとつ、小さな気づきを大切にしてみてください。それぞれの努力が、大きな安心感につながります。
事実と気づきのバランス
事実とは、私たちの心の地図。気づきは、そこに立つ道標のようなものです。この二つを優しく結びつけることで、普段は聞こえにくい私たち自身の心の声が、静かに呼び覚まされます。
仕事や家事と両立しながら勉強するのは大変。でも、ポイントをおさえた教材があれば時間を有効に使えます。
介護福祉士の国家試験に合格するならこのテキスト1冊だけで大丈夫!【受かるんです】“今年こそ合格したい” その気持ちを後押ししてくれるのが、この一冊です。
「事実」は、出来事をそのまま記録したもので、日時や場所、行動、数値などをシンプルに示します。一方で、「気づき」は、そこに込められた意味や変化の兆しを教えてくれるもの。進むべき方向やリスク、次に考えるべき仮説などが含まれます。この二つを混同せず、はっきり分けて書くことで誤解を防ぐことができます。
- 事実:
9時、居間。ご利用者が杖を使って10メートル歩行。ふらつきなし。休憩1回。 - 気づき:
自発的に立ち上がる回数が増え、歩行への意欲が高まっています。午前中の痛みの訴えも減少しました。
さらに、前日や先週との比較を加えることで、より分かりやすい方向性を見つけることができます。まずは「分けて書く」ことから始めてみましょう。
大切なのは、完璧にやり遂げることではなく、小さなステップから始めること。一歩ずつ進んでいけばいいのです。お忙しい毎日の中でも、ほんの少しの工夫で日々の気づきが深まることでしょう。
- 事実と気づきを分けて書きましょう。
- 以前のデータと比較してみましょう。
- 一度に全部やらなくても大丈夫、一歩ずつでOK。
日々の中で、少しずつ進むことが大切です。一緒に頑張りましょう。
事実の切り出しと感情の分離
事実を淡々と記録するだけでなく、そこにちょっとした工夫や気づきを添えることで、読み手の方々が自分を責めずに受け止められるようになると良いですね。例えば、心がほんの少し沈んでいるように見える時もあります。その場合、「朝食時に『いらない』と短く答えられ、眉間にしわが見られました。ここ数日、朝食への意欲が低下しているように感じます。」といった形で、具体的な観察から状況を記録することが大切です。そして、自分の感情や気づきは別の箇所に、「対応後には、声かけの頻度を落とした結果、少し落ち着いた様子を見せてくださいました。」と記すことができます。
また、ご高齢者の方が前向きな行動を取られたときには、それを温かく記録しましょう。「午前11時に廊下を20m歩かれました。その際、休憩なしで、呼吸が苦しいとの訴えもありませんでした。」と具体的に記録します。
- 状況を具体的に記載することで、読み手の共感を得やすくします
- 時間的な余裕のない場面でも、簡潔に記録を残しましょう
- 自分の感情や気づきは別の欄に書くことで整理整頓を
「すべてを完璧にする必要はありません。一つのステップだけでも、一歩踏み出してみてください。」と、日々の業務に取り組まれる皆様を応援する姿勢を持ちながら、記録を続けてみてくださいね。
記録に見える変化を言語化
日々の記録の中の小さな変化。その一つひとつに、優しい言葉を添えてみませんか。言葉にすることで、普段は気づかずに通り過ぎてしまう自分の成長を、そっと手のひらに感じることができるようになります。
仕事や家事と両立しながら勉強するのは大変。でも、ポイントをおさえた教材があれば時間を有効に使えます。
介護福祉士の国家試験に合格するならこのテキスト1冊だけで大丈夫!【受かるんです】“今年こそ合格したい” その気持ちを後押ししてくれるのが、この一冊です。
介護記録は、“変化の記録”。昨日との違い、いつもとの違いを優しく言葉にしてみましょう。この変化は、「頻度」「強度」「時間」「支援量」「ご本人の選択」に注目すると、整理がしやすくなります。
- 昼食時に、主食を8割召し上がり、副菜も完食。咀嚼時の眉間のしわが消え、食後も胃の不快感がないと見受けられました。
- 先週は主食の摂取量が5割だったのに対し、今日は8割。新しい姿勢調整が効果的だったようです。
ご本人の表情や声も合わせて記録すると、チーム内での情報共有がよりスムーズに。「更衣後に笑顔で『温かくて気持ちいい』とおっしゃいました。」という具体的な表現は大切です。
また、時間の経過とともに変化を追うと、未来の方向性が見えてきます。
夜間の覚醒が3回から1回に減少し、再び眠りにつくのが早くなっています。
こうした小さな違いを積み重ねていくことが、リスクの早期発見にもつながります。一度にすべてをこなそうとせず、少しずつ、一歩ずつ取り組んでみてください。それが、穏やかで実りある介護の一助となるでしょう。
本人の声を直接書く工夫
足が重たいと感じた時の対応
入浴前の更衣時に、ご高齢者の方がこんな思いを話されました。
- 意向:
足が重く感じるため、歩行は控えたい - 理由:
無理をすると疲れが溜まりそう - 条件:
必要な時は車いすを使いたい、との意向
このようなお声がけをいただくと、少し心が軽くなるかもしれません。すべてを完璧にこなす必要はありません。一歩だけでも前に進むことが大切です。
- 負担にならない範囲内で工夫を探してみる
- 他の方に優しく手を差し伸べてもらう準備をしておく
- 必要があれば無理せずサポートを受け入れる
自分を責めずに、小さな一歩を大切にしていきましょう。「全部やらなくていい」という気持ちで、少しずつ取り組んでみましょう。
安心感を生む読みやすさ
読みやすさは、心の中に小さな安心を灯す大切な第一歩です。文字と文字との間にゆとりを持たせることや、見やすいフォントの選択が、あなた自身のペースで物事を理解する心地よさを作り出します。
読みやすさは、手に取る安心感をもたらします。情報は一つずつ、短い文で、そして適度に改行を入れることで、頭の中が一杯にならずに受け取ることができます。最初に結論を、次にその理由を記すと、忙しい日々の中でもすんなりと心に届きます。
- 結論:
午後は穏やかに過ごされています。 - 事実:
13時には居間でテレビを1時間観賞、途中で「痛い」という発言はありませんでした。15時には杖を使って10分間の散歩も。 - 気づき:
日中の活動量が増えても、以前より疲労の訴えが減少しています。 - 対応:
夕食前の水分摂取を200ml続けましょう。 - 連絡:
看護チームと共有済みです。
数字や時刻、固有名詞を使うことで、誤解が減り、理解が深まります。また、否定的な言葉は避け、温かみのある表現を選びましょう。例えば、「拒否」は「今回は見送るご意向」のように。これにより、読み手に安心感を与えると同時に、現場での信頼の基盤を築くことができます。
このアプローチは、ご高齢者やご利用者への敬意と尊厳を忘れずに、日々の忙しさの中でも小さな気づきや安心感をもたらします。すべてを完璧にしようとしなくて大丈夫です。ただ、一歩一歩進んでいくことが大切です。
見出しの役割を意識する
見出しは、段落の要点を示す「ナビゲーション」として大切な役割を果たします。これにより、読み手は全体の内容を把握しやすくなります。特におすすめなのは、生活の主要な要素ごとに小見出しを設定することです。「食事」「排泄」「睡眠」「移動」「服薬」「気分・表情」「ご家族とのやりとり」といった具体的なカテゴリを固定するのです。
たとえば、「食事」の見出しの下には、簡潔な結論として「主食は8割摂取、咀嚼は安定している」といった情報を記載します。その後に、事実と気づきを分けて整理します。キーワードとして「転倒予防」「疼痛」「リハ意欲」などを添えると、情報を容易に検索できるようになります。
見出しは、情報の「約束事」としての役割を担っています。どなたが書いても、情報が一定の順番で提示されることで、読み手は常に安心感を持ち、情報の抜けが少なくなります。
仕事や家事と両立しながら勉強するのは大変。でも、ポイントをおさえた教材があれば時間を有効に使えます。
介護福祉士の国家試験に合格するならこのテキスト1冊だけで大丈夫!【受かるんです】“今年こそ合格したい” その気持ちを後押ししてくれるのが、この一冊です。
まとめ
過去の出来事を静かに振り返りながら、あなたの心に寄り添う小さな発見をまとめてみました。明日への一歩が少しでも軽やかになるお手伝いができれば幸いです。
記録をつけるときのポイントは、事実と気づきを分け、それぞれを短く表現することです。また、読み手に合わせて情報を整理すると良いでしょう。あなたの心配りは、言葉にすることでよりしっかり伝わります。以下に、見直しに便利なチェックリストをご用意しました。
- 主語と時制が整っているか
- 5W1H(日時、場所、行動、回数)が含まれているか
- 事実と気づきが分かれているか
- あなたの声や表情、考えが一言伝えられているか
- 変化が以前との比較で示されているか(前日、先週、基準など)
- 数字や固有名詞、連絡先が明確に記されているか
- 略語や専門用語を避け、平易な表現になっているか
- ご高齢者とご家族への敬意が保たれているか
- 観察者、記録日、情報源が明記されているか
- 次のステップが記載されているか(対応、依頼、共有先など)
記録が苦手でも心配いりません。今日、ほんの一行から始めてみてください。その小さな気づきが、介護の現場とご家族に安心をもたらし、大きな支えとなります。
「介護 記録 書き方」や「伝わる記録」、「事実と気づき」で検索すると良いヒントが見つかります。明日への申し送りが少しだけ軽くなりますように。
急がしい毎日の中でも、このアドバイスが少しでもあなたの助けになればと思います。敬意を込めて、ご高齢者やご利用者様に接するためにお役立てください。
これから介護の仕事を始めたい方も、もっと自分に合った職場を探したい方も、条件からしっかり比較できると安心ですよね。
介護士の求人、募集は【レバウェル介護】勤務地・給与・働き方など、あなたに合った条件をもとに探せるので、無理なく続けられる環境が見つかりやすいです。
このブログを書いている「まきこむ」と申します。
介護支援専門員(ケアマネジャー)として働きながら、趣味で創作活動も楽しんでいます。
介護にまつわる悩みや、日々の気づき、そして「やさしい未来を一緒に歩むためのヒント」を、このブログにそっと詰め込んでいます。
読んでくださった方の心が、少しでも軽くなるように。そんな思いを込めて、言葉を紡いでいます。
どうぞ、ゆっくりと遊びにきてくださいね。






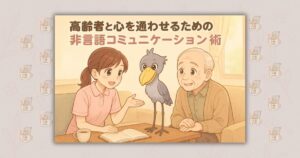
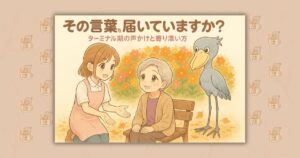

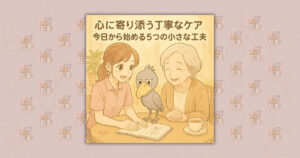
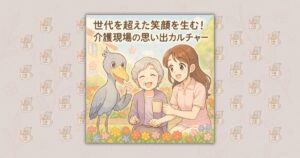

コメント